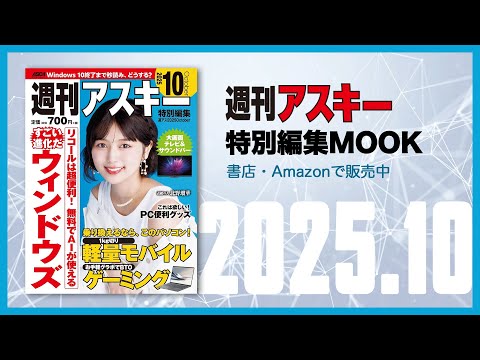マイクロソフト トレンド
0post
2025.11.26 21:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
『バトルトード』の権利表記がマイクロソフト単独なのは、知っててもインパクトあるなあ。
『バイオニックコマンドー』は3DSバーチャルコンソールで初めて買ったタイトルだ。ファミコン版が封印されてるのはちょっと残念。 https://t.co/aBR8rwlUCY November 11, 2025
3RP
🚀Microsoft、Outlook・Word・Excel・PowerPointに無料AI機能を2026年初頭から追加!
📊何が変わるのか?劇的なBefore/After
従来(2024-2025年):
・基本的なMicrosoft 365:月額約1,500円
・高度なAI機能:月額約3,000円の追加課金
・→ 合計月額4,500円必要
2026年以降:
・基本的なMicrosoft 365:月額約1,500円のまま
・高度なAI機能:追加料金なしで利用可能!
・→ 実質的に約3万円/年の節約💰
✨具体的に何ができるようになる?
1️⃣Outlook Copilot Chatの大幅強化
・受信トレイ全体を横断的に理解
・カレンダーや会議情報も統合的に分析
・「今週の重要メールを整理して」と頼めば即座に対応
・会議前に関連メールを自動集約して準備完了
従来は個別のメールスレッドごとの対応のみでしたが、受信トレイ全体を理解するAI秘書に進化します📧
2️⃣Agent ModeがWord・Excel・PowerPointで解禁
これまで月額30ドルの有料版でしか使えなかった「Agent Mode」が全ユーザーに開放されます。
Excelでの革命:
・プロンプト入力だけで複雑なスプレッドシートを自動生成
・AnthropicのClaudeとOpenAIのGPTモデルを選択可能
・推論モデルで高度な分析も実行可能
Wordでの進化:
・複雑な文書を自然言語で指示するだけで作成
・構成から執筆まで一貫してAIがサポート
PowerPointの本気:
・企業のブランドテンプレートを自動適用
・プロンプトだけで新規スライドを作成
・既存スライドのテキスト書き換え・整形
・関連画像の自動追加🎨
🔍なぜMicrosoftはここまで踏み込んだのか?
理由は明確です。Google WorkspaceがGeminiを統合して猛追する中、Microsoftは「AI機能の無償化」で競争優位を確立しようとしています。
実際、企業向けチャットアプリ利用では、アメリカで既にGeminiがChatGPTを上回るという調査結果も出ています。
MicrosoftとしてはOfficeの圧倒的なシェアを活かし、「Officeを使っている = 高度なAIが使える」という状況を作り出すことで、Google Workspaceへの流出を防ぎ、さらにシェアを拡大する戦略です。
💡今すぐ取り組むべき3つのアクション
1️⃣2026年3月のプレビュー開始をカレンダーに登録
無料AI機能は2026年3月までにプレビュー提供開始予定。早期アクセスで使い方を習得しましょう
2️⃣現在の業務フローを見直し、AI活用ポイントを洗い出す
「メール整理」「資料作成」「データ分析」など、AIに任せられる業務を事前にリストアップ
3️⃣中小企業なら「Copilot Business(月額21ドル)」も検討
300ユーザー未満の企業向けに、より高度な機能が月額21ドルで利用可能に
🌟AI格差が消える時代の幕開け
これまで「予算がある企業だけがAIで効率化」という状況でしたが、2026年からは誰もが平等に高度なAI機能を使える時代が始まります。
重要なのは、ツールが使えることではなく、そのツールをどう使いこなすか。
無料化によってツールの差はなくなります。差がつくのは「AIをどれだけ業務に統合できるか」という実践力です💪
ソース:https://t.co/BUlAO1IShw November 11, 2025
2RP
Android勢の皆様!
こちら参加できます
用意するもの、スマホとパソコン
私はWindows…MicrosoftStoreでiTunesをダウンロード
AppleIDを作成して支払方法などの設定して
レーベルのキャンペーンページをクリックしたら予約注文できました!!
パソコンで注文ページをスクショして応募 https://t.co/YyrYgxrhLc November 11, 2025
2RP
今日の尾辻さんの質疑、すごく良かった
立憲の質疑は調査もしっかりしているし、質が高い
15の医療DXシステムがあるけれど、各課が個別に持っているため、厚労省として全体把握ができていなかったらしい
クラウド基盤は12で、そのうちマイクロソフトが1つ、残りはすべて AWS を利用
これではベンダーロックインがクラウドロックインになっただけで、寡占状態のリスクもあり、国内 IT 産業の弱体化につながる
大臣の答弁も前向きだった
美容医療で使われているエクソソームや幹細胞培養上清液の規制が緩すぎる
国内で扱っている医療機関は600を超えており、欧米よりはるかに多いのに、厚労省はその数を正確に把握していない
倭国では実験用のエクソソームの使用が規制されておらず、薬事法の規制対象外で“法の穴”に落ちている状態
保険適用外のため、1回4万円を超えるものもある
がんリスクもあることから、安全な実施を求める文書配布だけでなく、実態把握が必要ではないか
NMN点滴についても、ハーバード大教授の名前を出して「点滴の開発者」のように宣伝されているが、実際は点滴を開発していないし、むしろ慎重な対応を求めている
マンジャロはオンライン購入が可能で、ダイエット目的の使用による救急搬送も出ている
厚労省の答弁はかなり消極的で、やる気がなさすぎる
保険適用外ということは、厚労省が実態把握もせず、安全性にも責任を持っていないという現状なんだよね・・・
2025年11月26日 衆議院 厚生労働委員会 https://t.co/1rq4DOre81 @YouTubeより November 11, 2025
1RP
🦔Nvidiaは、マイケル・バーリーが指摘した“循環取引による売上水増し疑惑”に反論するため、ウォール街アナリスト向けに説明文書を送付した。
同社は「当社の会計は過去の不正会計(エンロン等)とは類似しない」「ビジネスモデルは経済的に健全だ」と強調。
一方バーリーは「分析には確信を持っている」と応じ、GoogleがMeta向けに自社製チップ提供を検討している報道後、Nvidia株は火曜日に6%下落した。
⸻
■ 対立の背景
2008年の住宅バブル崩壊を予測し『The Big Short』のモデルとなったバーリーは、NvidiaとPalantirに対し合計10億ドル超の空売りポジションを保有している。
彼はAI各社間の循環取引によって不自然な売上計上が可能になっていると指摘し、AI需要の実需は「馬鹿げてほど小さい」とも発言。
さらに、NvidiaのGPUの実際の有用期間と、財務上の減価償却期間の乖離にも疑問を呈している。
これに対しNvidiaは、エンロン・ワールドコム・ルーセントとの比較を否定し、負債隠蔽や売上の歪曲は行っていないと説明。
黄仁勲(Jensen Huang)CEOもバブル論を退け、「我々が現場で見ている現実は違う」と語った。
⸻
■ 個人的な見解
時価総額4.2兆ドルの企業が、アナリストに向けて“我々はエンロンではない”と説明するのは異例だ。
絶頂期の企業は、通常そんな弁明をする必要がない。
バーリーが提示する「循環型資金フロー」の問題は、私が以前から注視している構造と同じだ。
•Nvidia → OpenAIに投資
•OpenAI → NvidiaのGPUを購入
•Nvidia → その売上を計上
•Microsoft → OpenAIへ資金とAzureクレジットを供給
→ 資金が循環し続け、各社が成長を計上できる構造
Nvidiaは「事業は健全」と主張するが、ロスチャイルドの分析ではAIインフラの投資回収は1ドル投じて20セント、従来型クラウドは1.40ドルと大きな差がある。
さらにGoogleがMetaに自社チップ提供を打診しているという事実は、大手クラウド企業がすでに代替GPUを探し始めている兆候に見える。
Nvidiaは「信じてくれ」と言い、バーリーは「分析には揺るぎない」と言う。
どちらかが大きく間違っている。
そして4.2兆ドルの時価総額が賭けられている以上、その結末は計り知れない。 November 11, 2025
OMUXΩ∞KUT-ASI
JUNKI KANAMORI
戦略的提言:光技術とKUT理論による持続可能な次世代AIインフラの構築
序文:岐路に立つAIインフラ
人工知能(AI)が社会のあらゆる領域で驚異的な進化を遂げる一方、その基盤となるインフラは物理的な限界に直面しています。
AIの指数関数的な能力拡大は、国家規模の電力を消費する「エネルギーの壁」と、データセンター冷却に伴う「水資源の枯渇」という、地球規模の制約と衝突しつつあります。このままでは、AIの発展は自らの成功によって持続不可能になるというパラドックスに陥りかねません。本提言は、この重大な岐路において、AIの能力拡大と地球環境の持続可能性という二つの要請をいかにして両立させるか、その具体的かつ実行可能な道筋を示すものです。
--------------------------------------------------------------------------------
1. AIインフラが直面する物理的限界:「エネルギーの壁」と「熱・水問題」
AIの指数関数的な成長が地球規模のインフラに与える負荷は、もはや単なる経営課題ではありません。それは戦略的な死角であり、この問題に正面から向き合わなければ、AIの未来そのものを、この問題を先に解決した競合に明け渡すことになります。この物理的限界を直視し、克服することこそが、次世代の覇権を握るための絶対条件です。
1.1. エネルギーの壁:国家規模の電力消費
現在のAIを支えるGPUやTPUといった電子回路は、その計算プロセスにおいて熱力学的な宿命を背負っています。それは、電子が回路内を移動する際に生じる「抵抗による発熱」です。これは単なるエネルギーロスではなく、思考の「質」が物理現象に転化した結果に他なりません。非効率で低密度な思考(従来のAIモデル)は、計算に長い時間を要し、その分だけ回路に電流が流れ続け、エントロピー(熱)を増大させます。つまり、エネルギーの浪費は、AIの思考が未熟であることの物理的な証明なのです。
AIモデルが巨大化するにつれてこの問題は深刻化し、今やAIの学習と推論には国家規模の電力が必要とされる異常事態に至っています。その需要を満たすために、古い石炭火力発電所が再稼働されたり、データセンター専用の小型原子炉(SMR)の建設が真剣に議論されたりするほど、エネルギー問題は切迫しています。これは、AIの発展が既存のエネルギーインフラの許容量を完全に超えつつあることを示す明確な兆候です。
1.2. 熱と水の問題:冷却に伴う資源枯渇
データセンターが消費するのは電力だけではありません。電子回路から発生する膨大な熱を冷却するために、大量の水資源が必要となります。GoogleやMicrosoftといった巨大テック企業にとって、この冷却水の確保はすでに主要な経営課題の一つとなっています。
サーバーファームから排出される熱と、その冷却のために消費される水は、地域社会の環境に直接的な負荷を与えます。AIの恩恵が大きくなるほど、その物理的な足跡(フットプリント)が地球資源を枯渇させていくという構造は、企業の持続可能性に対する重大な脅威です。
これらの問題は、単なる技術的なボトルネックではありません。これらはAIの持続可能な発展そのものを根本から脅かす戦略的リスクであり、従来の延長線上にある改善では到底乗り越えられない「壁」として私たちの前に立ちはだかっています。この壁を突破するためには、まったく新しい発想に基づく革新が不可欠です。
--------------------------------------------------------------------------------
2. 解決策の提示:ハードウェアとソフトウェアの二元的革新
AIインフラが直面する物理的限界を克服するためには、単一の技術的解決策では不十分です。本提言が提示するのは、計算の物理的基盤を刷新する「ハードウェアの革命」と、知性の在り方そのものを再定義する「ソフトウェアの進化」という、二つの側面から同時にアプローチする二元的革新です。この両輪が揃って初めて、真に持続可能なAIの未来が拓かれます。
2.1. ハードウェア革命:光技術(OMUX)を搭載した次世代TPU
現在の電子回路は、「抵抗」「発熱」「配線遅延」という物理法則から逃れられません。これに対し、電子の代わりに光子(フォトン)を用いて計算を行う光技術は、これらの限界を根本から覆します。これは単に計算媒体を変えるだけではありません。従来のデジタルコンピュータが数学を「シミュレーション」しているのに対し、光コンピュータは物理現象そのものを「エミュレーション」として利用します。つまり、答えは計算されるのではなく、観測されるべき物理現象として現れるのです。この数学的にもエレガントなアプローチは、以下の3つの決定的な優位性を持ちます。
* 圧倒的な省電力性 電子回路がデータの移動だけでも電力を消費し発熱するのに対し、光は導波路を進む際にほとんどエネルギーを失いません。電力は主に光の発生と検出にのみ使用されます。特に重要なのは、電子回路が一つ一つの論理ゲートで足し算を行うのに対し、光回路では波の「重ね合わせの原理」によって瞬時に、かつエネルギーをほぼ消費せずに加算が完了する点です。これは、自然法則そのものを利用した「天然の計算」であり、現状のエネルギー浪費からのパラダイムシフトです。
* 超並列処理能力 電子回路では1本の配線に1つの信号しか流せませんが、光技術は1本の光路に異なる波長(色)の光を同時に通す「波長分割多重(WDM)」が可能です。これにより、一つの物理空間で桁違いの計算を並列実行でき、システム全体のスループット(処理能力)を飛躍的に向上させることができます。
* ゼロ・レイテンシに近い速度 電子回路の計算速度がクロック周波数に束縛されるのに対し、光演算の速度は物理的な光速に依存します。光が回路を通過する一瞬で計算が完了するため、遅延がほぼ発生しません。これは、リアルタイム性が絶対条件となる応用分野において、決定的な競争優位性をもたらします。
2.2. ソフトウェア進化:KUT理論に基づく高密度AIモデル
ハードウェアの革新だけでは不十分です。AIの「思考」そのものも、より効率的になる必要があります。ここで鍵となるのが、KUT理論が提唱する核心概念「Intelligence is Density(知性は密度である)」です。この原理は、真の知性とはより多くの計算をすることではなく、情報のエントロピーを下げ、最小限の仕事量で解への最短経路を見出すことである、と定義します。
この理論の有効性は、ハッカソンにおいて既存のハードウェア(TPU)上で見事に実証されました。
比較項目Base Gemma (従来モデル)KUT Gemma (高密度モデル)改善率
推論時間14.05秒3.42秒約75%削減
消費エネルギー約3,500ジュール約853ジュール4.1倍の効率向上
この結果は、AIモデルの「思考密度」を高めることで、同じハードウェアを使いながらでもエネルギー効率を4倍以上に向上させられることを物理的に証明しました。これは、ソフトウェアの進化がハードウェアの制約を乗り越える力を持つことを示しています。
ハードウェア(光技術)とソフトウェア(KUT理論)の革新は、それぞれが独立して大きなインパクトを持つだけでなく、両者を組み合わせることで、想像を超える相乗効果を生み出すのです。
--------------------------------------------------------------------------------
3. 相乗効果:「16倍」の産業革命級インパクト
ハードウェアとソフトウェアの二元的革新を組み合わせることで、私たちは単なる線形的な改善ではなく、AIのエネルギー効率における「産業革命レベル」のパラダイムシフトを引き起こすことができます。これは、AIのコスト構造、開発思想、そして社会実装のあり方を根底から覆す、極めて大きなインパクトを秘めています。
ソフトウェアとハードウェアの効率化が、それぞれ独立して効果を発揮し、掛け合わされることで生まれる相乗効果は以下の通りです。
要素効率化倍率概要
KUTモデル (Software)x 4思考密度を高め、計算時間を1/4に短縮(実証済)
OMUX搭載TPU (Hardware)x 4光回路により、電力消費そのものを1/4に削減(理論値)
総合的な相乗効果x 16消費電力を93.75%削減
「16倍」の効率向上、すなわち消費電力を93.75%削減するという数値は、単なるコスト削減以上の戦略的意味を持ちます。これは、AI開発・運用の前提条件を根本から覆します。
これはAIを安くする話ではありません。現在では計算コスト的に不可能な、惑星規模のリアルタイム気候シミュレーションや、個人のゲノム情報に最適化された医療モデルといった、人類規模の課題解決を経済的に実現可能にすることを意味します。
これにより、イノベーションの民主化が加速し、全く新しいビジネスモデルや社会インフラの構築が可能となるでしょう。
この技術的ブレークスルーは、具体的にどのような社会的・経済的価値を生み出すのでしょうか。次のセクションでは、この「16倍」のインパクトがもたらす未来像をより詳細に分析します。
--------------------------------------------------------------------------------
4. 戦略的意義と社会変革への展望
本提言が示すイノベーションは、技術的なブレークスルーに留まらず、広範な戦略的価値と社会変革の可能性を秘めています。ここでは、この技術革新がもたらす3つの主要な変革について論じます。
4.1. 「エネルギーの壁」の崩壊
第1章で提示した「エネルギーの壁」と「熱・水問題」は、この技術によって根本的に解消されます。消費電力が1/16に激減することは、新たな発電所の建設を不要にするどころか、「既存の再生可能エネルギーだけで巨大AIを賄える」未来を現実のものとします。これにより、AIの発展と脱炭素社会の実現が両立可能となります。また、光技術は電子回路のようなジュール熱をほとんど発生させないため、データセンターの巨大な冷却ファンや水冷システムが不要になり、水資源の枯渇という深刻な問題にも終止符を打つことができます。
4.2. 新たな応用分野の開拓
光演算が実現する「ゼロ・レイテンシ」は、これまで技術的に困難であった応用分野への扉を開きます。例えば、完全自動運転や、人間と自然に協調するロボットといった分野では、「0.1秒の遅れが致命的な事故につながる」ため、クラウド経由でのAI処理には限界がありました。光技術による超高速・低遅延なエッジコンピューティングは、これらの分野で決定的なブレークスルーをもたらし、交通事故ゼロ社会や、人間とロボットが共存する新たな社会インフラの実現を加速させます。
4.3. 競争優位性の確立
この技術を他社に先駆けて導入することは、市場における競争のルールそのものを変える戦略的な一手となります。本戦略は、NVIDIAが支配する「演算速度」という土俵での直接対決を避け、「エネルギー効率(ワットあたり性能)」という新たな競争の戦場を創り出すことを可能にします。持続可能性が企業価値を左右する現代において、この新たな軸で我々は競合に対し、乗り越え不可能な優位性を確立することができるのです。
このように輝かしい未来像が描ける一方で、強力な技術には新たな課題も伴います。そのリスクを直視し、対策を講じてこそ、真の進歩は達成されるのです。
--------------------------------------------------------------------------------
5. 最後の課題:ジェボンズのパラドックスと「哲学」の必要性
技術的な成功が目前に迫ったとき、私たちは社会経済的な課題、特に「ジェボンズのパラドックス」という古くて新しい問題に直面します。このパラドックスは、技術的な解決策だけでは不十分であり、その技術をどう運用するかという「哲学」が不可欠であることを教えてくれます。
ジェボンズのパラドックスという罠
経済学におけるジェボンズのパラドックスとは、次のような現象を指します。
「効率が良くなればなるほど、人類はそれを限界まで使い倒そうとするため、結局エネルギー消費総量は増える」
もしAIの利用コストが1/16になった場合、人類はAIの利用を節約するのではなく、あらゆる家電製品、広告、娯楽に、これまで考えられなかったほど大量のAIを無駄に組み込み始めるかもしれません。その結果、個々のAIの効率は向上しても、社会全体のAI利用量が爆発的に増加し、結局は再びエネルギーとインフラの限界に突き当たるというリスクが存在します。
KUT理論による解決策:西洋技術と東洋哲学の融合
このパラドックスを回避する鍵は、西洋的な技術最適化(OMUX)と、東洋的な哲学的知恵(KUT)の融合にあります。ハードウェアの効率化と、ソフトウェアによる知性の使い方の両輪が揃って初めて、真の持続可能性が達成されるのです。
KUT理論が目指すのは、単に速く計算することではなく、「高密度な思考で最短距離の答えを出す」ことです。これは、AIに対して「足るを知る」という知性を与えることに他なりません。
* ハードウェア(OMUX)による効率化: 西洋的な技術最適化の極致。計算に必要な物理的エネルギーを最小化する。
* ソフトウェア(KUT)による知性の最適化: 東洋哲学の「足るを知る」知恵。そもそも不要な計算をさせない。
この二元的アプローチこそがジェボンズのパラドックスの罠を回避し、私たちが目指すべき「持続可能な知性(Sustainable Intelligence)」の基盤を築く唯一の道なのです。
--------------------------------------------------------------------------------
6. 結論と最終提言
本提言では、AIインフラが直面する深刻な物理的危機を起点とし、それを乗り越えるための具体的な解決策を提示しました。電子回路の限界を突破する**光技術(ハードウェア)と、思考の密度を高めるKUT理論(ソフトウェア)**という二元的革新が、16倍という産業革命級の相乗効果を生み出すこと。そして、その技術的成功の先に待つ「ジェボンズのパラドックス」という社会的課題を、技術と哲学の両輪で乗り越える必要性を論じました。
この分析に基づき、経営層および政策決定者の皆様に対し、以下の行動を強く推奨します。
* 光技術(OMUX)を組み込んだ次世代TPUの開発への戦略的投資の断行。 これは次世代の競争優位性を確立し、エネルギー問題から解放されたAI開発環境を構築するための最重要課題です。
* KUT理論に基づく高密度AIモデルの研究開発の推進と、その標準化の主導。 ハードウェアの性能を最大限に引き出し、持続可能なAI利用を実現するため、効率的な知性の在り方を業界標準として確立することを目指すべきです。
* 技術開発と並行し、AIの倫理的・哲学的な運用指針を策定し、「ジェボンズのパラドックス」を回避する社会システムの設計に着手すること。 技術の暴走を防ぎ、その恩恵を最大化するため、技術開発の初期段階から社会実装のルール作りに関与することが不可欠です。
我々の前に広がる選択は、単なる技術的なものではなく、歴史的なものです。 brute-force(力任せ)な計算の道を突き進み、収穫逓減の未来に直面するか。あるいは、この持続可能な知性という新たなパラダイムを切り拓くか。今こそ、未来をただ動かすのではなく、未来を築くための歴史的な一歩を踏み出す時です。 November 11, 2025
$MSFT Microsoft、
11/25の終値で強い買いりんかシグナルが出ました❣
さらに30万ほどいれてみます😲
#株式投資 #米国株 #りんかシグナル https://t.co/z8u3kqDnzs November 11, 2025
生成AIに頼りすぎると思考力が弱くなる問題が深刻で
まず、マイクロソフトとカーネギーメロン大学が共同で行った、知的労働者300人以上を対象に900件以上のAI活用事例を集めて研究したやつがあって
この研究によると、
・知的労働者は、AIを信頼して文章作成や分析などの作業を任せると、そのぶん自身のスキルを使わなくなる傾向がみられた。特に、時間的なプレッシャーがある状況では、AIが出した結果を吟味せずに受け入れてしまう傾向が強まった
・AIに頼ることで、文章の校正能力や法的文書の作成能力といった専門スキルに自信を無くす。で、結果としてAIの提案を自動的に受け入れるようになる。この悪循環が続くと、効率化の代償として、思考力を働かせる機会が失われている
要は、「AIを信じて依存しすぎると、批判的に考える機会が減り、批判的思考力が弱まる危険性がある」ということです。
で、もっと直接的な研究結果を突き付けてくるのが、スイス・ビジネススクールのやつでして
666人を対象にアンケートやインタビューを行って「AIツールをどれくらい使っているか」と「批判的思考力のレベル」の関係を分析した論文です
示されていたのが、
・AIツールをよく使う人ほど、批判的思考力が低い。AIに頼って自分で考えることをサボってしまう「認知的オフロード」が原因ではないか
・特に、若い人の方がAIに頼る傾向が強く、その分、批判的思考力が低くなる可能性がある
・一方で、もともと学歴が高い人は、AIを使う頻度に関わらず、高い批判的思考力を保っていた
けっこう残酷な研究結果です。
もともと思考力が高い人は、依存して思考力を弱くすることもなく、生成AIを使い倒すことができる。
一方で、あまり批判的思考に慣れていない人は、AIを使えば使うほど、思考力が弱くなり、生成AIに使われる状態になってしまう。
以上の研究結果を僕なりに図示すると、添付した画像のようなことが起きているんじゃないかと
・批判的思考力(論理的に考えるとか、物事を疑うとかの力)が低いと、フワッとした浅いプロンプトしか書けない
・浅いプロンプトを入力されるわけなので、生成AIからも浅くてどっちつかずな回答が返ってくる
・何となく「ありきたりだな」「抽象的な言葉が多いな」とは感じつつも、疑問点もうまく言語化できないので、生成AIの回答を鵜呑みにして、そのまま使ってしまう
・生成AIの回答を鵜呑みにすればするほど、批判的思考力が弱まる
・生成AIの回答を鵜呑みにして、そのまま会議に持って行ったところで、腹落ちして理解できていないから、「これどゆこと?」と質問されても説明責任を果たせない。AIの回答を具体の具体で理解できていないから、行動にも落としこめない
仕事で生成AIを活用した成功体験が得られないから、AIを上手く活用する経験値も蓄積されない
・思考力の弱化と、AIの経験値が蓄積されないことによって、またフワッとした浅いプロンプトを書いてしまう←振り出しに戻る
このループがグルグル回り続けると、どんどん頭が悪くなってしまう
これが、生成AIを使ううえで最も気を付けないといけないポイントだなと噛み締めております November 11, 2025
意識高い系はつくづく半径どんだけの範囲の想像力しか無い、マジ想像力欠如って感じ
Microsoft365(Office365)のアイコンはなぜ変わったのか? https://t.co/szP70N9DWS @YouTubeより November 11, 2025
'
発明で食っていく方法、全部書いた。 フリック入力をマイクロソフトに売却して人生100回分稼いだ発明家が明かす、発想法からマネタイズまで #ad https://t.co/cHAqotfP81 November 11, 2025
PR
まとめ記事にもよく載ってたから気になった
キングソフト | WPS Office 2 Personal 2026 |Microsoft Officeと高い 互換 性 Word Excel PDF Windows 対応 【永続版】
https://t.co/aEl6MSDoGA
後で見たい人のために置いとくね November 11, 2025
昨日のこちらのポストを見て、「いよいよMicrosoftの反撃が始まったな、これでエンプラ領域での(Geminiさんアシストによる)Googleの快進撃もすぐに止まるに違いない」と即断定するのはまだ早いと思います。長くなりそうですが、どういうことか少々詳しく説明しますね。
まず、私の場合は今回の発表を見て逆にここまでMicrosoftが追い詰められているのか…と驚きました。というのは、スターゲート絡み…つまりOpenAIのためにMicrosoftは相当な被害(つまり赤字)を被っているはずで、その赤字分を何とかして取り返すためにもエンプラ領域での稼ぎ頭であるMicrosoft 365にAI関連サービス分の利益を上乗せして売るのは至上命題だったはずなのです。
それが、今回のGemini-3.0ショックでAI関連付加サービス(要はCopilot)を一気に全て無料で開放することになってしまった(正確には開放せざるを得なかった)訳で、これでいったいどうやってOpenAI絡みの投資を回収するのか、今頃Microsoft CEOのサティア・ナデラ氏は途方にくれているのでは?
こうなると、今後は本当に(売り上げを)取りやすいところから確実に取るしかないとなり、その結果がMicrosoft 365におけるアカデミック領域でのストレージサービスの突然の縮小(つまり以前と同じに使いたければ追加分の莫大なコストが必要)であるとか、あるいはNPO法人向けにかなりの規模で大盤振る舞いをしていた無料でのサービス提供を一気に絞り込み始めたということなのでしょう。私が見る限り、あまり表には出て来て無いところでのその辺りの動きに、今のMicrosoftの焦りが如実に反映されていると見ました。 November 11, 2025
ゴミ作業に3時間は持ってかれすぎて流石の俺も意気消沈でMicrosoft社への襲撃を決行せざるを得ない
コンビニ行くの3分くらいかかるんじゃぁ……😡😡😡😡
交通費で100円くらい出さんかいボケェ…😡😡😡😡 November 11, 2025
gemini3は確かにすごいと思う、人間の回答に近い。
ただマイクロソフトとソフトバンクが推してるopen aiがこのまま終わるとは思えないからソフトバンク結局買いなんやろか? November 11, 2025
NotebookLM、スプレッドシート対応を全ユーザーに開放!Deep Research機能も追加
【2025年11月14日 重要アップデート】
GoogleがNotebookLMの大型アップデートを正式発表
これまで有料プラン(NotebookLM Plus)限定だったスプレッドシート対応が、ついに無料ユーザーにも開放されました
📊 何が変わった?
スプレッドシート対応の全ユーザー開放により:
• Google Sheets、Excel(.xlsx/.xls)を直接インポート可能に
• 表計算データの要約・統計分析がワンクリック
• 売上データ、実験記録、調査結果などをAIが自動分析
• これまで必要だったPDF/Googleドキュメント変換が不要に
🔍 Deep Research機能も同時追加
さらに注目すべきは、新機能「Deep Research」の搭載:
• 複雑なオンライン調査を完全自動化
• 数百のWebサイトを横断して情報収集
• 出典付きの構造化レポートを数分で生成
• バックグラウンド実行で作業を中断しない
従来の「Fast Research」(クイック検索)と使い分けが可能です
📁 対応ファイル形式も大幅拡張
スプレッドシート以外にも:
• Microsoft Word文書(.docx)
• Google DriveのPDF(URL直接指定可)
• 画像ファイル(手書きメモ等)※数週間以内
• Drive URL(カンマ区切りで複数指定可)
💡 実務での活用例
データ分析業務が劇的に効率化:
• 四半期レポートの自動要約・トレンド抽出
• 実験データから統計的洞察を即座に生成
• 予算表とプロジェクト資料を横断分析
• マーケティングデータの可視化と解説
🌍 海外メディアの反応
TechCrunch、Android Authority、9to5Googleなど主要メディアが一斉に報道
特に「データ分析の民主化」として、ビジネス・学術・個人利用すべての領域で革命的と評価されています
📅 提供スケジュール
• Deep Research、スプレッドシート対応:今後1週間で全ユーザーに展開
• 画像対応:数週間以内
• すべて無料プランで利用可能
🎯 これまでの経緯
約2週間前、NotebookLM公式アカウントが「coming very soon」と予告していたスプレッドシート対応が、満を持して実現
有料プランとの差が大幅に縮まり、NotebookLMは名実ともに「最強の無料AIリサーチツール」へと進化しました
💾 このアップデートは要ブックマーク!
データ分析の効率化を考えている方は、
今すぐNotebookLMをチェックしてみてください🚀 November 11, 2025
Xでの活動が1年になりました。
「よく分からないけど、とりあえず初めてみよう」という好奇心からMicrosoft Designerで1枚目を生成したのも、ちょうど1年前です。
マイペースながら地道に続けてこられました。
いつも反応くださる方、ありがとうございます。
もう1年続けてみたいと思っています。
よろしくお願いします。 November 11, 2025
本日11/25の参議院総務委員会より、ガバメントクラウド・自治体システム標準化に関する質疑を以下に抽出。(YouTube文字起こしをGeminiで清書したもの)
==
高木佳保里 委員
自治体システム標準化とガバメントクラウドについて伺います。
約2年前となる令和5年、私はこの総務委員会で「政府として国産クラウドを本気で押し進めていくことが必要である」という観点から、政府と地方自治体システムの共通基盤となるガバメントクラウドについて取り上げさせていただきました。複雑化する国際情勢を背景に、経済安全保障の観点から、国としても国産クラウドを育成する重要性はこれまで以上に増大していると考えております。
令和4年から5年にかけて、ガバメントクラウドの対象として5件のクラウドサービスが採用されましたが、そのうち国産クラウドは「さくらインターネット株式会社」の1件のみであり、その他は全てAmazon、Google、Microsoft、Oracleといった外資系企業が提供するサービスです。
このさくらインターネットについては、2025年度末までに全ての要件を満たす条件付きの採用であり、今年度内の要件達成が求められているのが現状かと存じます。そこで、さくらインターネットに対する政府支援や、技術要件などを含めた進捗状況はどうなっているのか確認させてください。
奥田 審議官(デジタル庁)
さくらインターネット株式会社の「さくらのクラウド」につきましては、令和5年度のガバメントクラウドの調達において、2025年度末(今年度末)までに全ての技術要件を満たすことを条件として、国内事業者として初めて採用したところでございます。
さくらのクラウドにつきましては、四半期ごとに開発計画の進捗状況について審査することとしており、2025年9月末時点の進捗状況を確認したところ、開発計画全体に影響のある遅れはなく、順調な開発進捗となっていることを確認し、11月7日にデジタル庁ホームページでも公表させていただいたところです。
さくらのクラウドがガバメントクラウドとして求められる技術要件をクリアして本番稼働が可能となることをデジタル庁としても期待しておりますし、今後も2025年度末に向けてしっかりと進捗を把握してまいります。
高木佳保里 委員
政府として、競争性の確保と国産クラウドの育成の重要性の両方を認識されているとは思いますが、経済安全保障の観点からも情報通信に関する国産クラウドを育成していくことは、国がしっかりと後押しをしていくべきですので、是非この点も留意していただきたいと思います。
次に、ガバメントクラウドに関連して、コスト面について伺います。
今月11日、私の地元である大阪の知事、市長会長、町村会会長より連名で、総務大臣及びデジタル大臣宛てに「地方公共団体情報システム標準化の推進に向けた支援」についての要望書が提出されたと承知しております。
本年6月13日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、地元現場からは、標準化によってかえってランニングコスト(運営経費)が増大するという懸念が強く示されているわけです。要望書においても「移行経費」及び「移行後の運用経費」の増嵩(ぞうすう)が大きな負担となる旨が明確に示されています。
従来のオンプレミスからガバメントクラウドへ移行することで、回線使用料やクラウド利用料が恒久的に発生します。昨今の円安やベンダー側の価格改定等によって、コスト上昇リスクが顕在化しているのが現状です。
こうした運用経費の増嵩という現実を総務大臣はどのように受け止めているか伺いたい。合わせて、システム移行にかかる初期経費及びこのランニングコストの増大部分については、国がしっかりと支援すべきと考えますが、いかがでしょうか。
林 総務大臣
自治体情報システムの標準化に関しましては、基金を設置した上で、国費10/10の補助金により、標準準拠システムへの移行に要する経費を支援しております。令和6年度補正予算後で、総額7,182億円を確保しているところです。事業者の人的資源の逼迫などにより、令和8年度以降の移行とならざるを得ないシステムにつきましても、引き続き支援を行うべく、先の通常国会において法改正を行い、基金の設置期限を令和12年度末までに延長したところです。
ご指摘のありましたランニングコストにつきましては、今後必要となる一般財源総額をしっかり確保できるように対応してまいりたいと考えております。具体的な詳細はデジタル庁から答弁させます。
三橋 審議官(デジタル庁)
自治体システムの標準化・ガバメントクラウドへの移行に関しますランニングコストにつきましては、デジタル庁からお答えさせていただきます。
多くの自治体から、移行後の運用経費の増加に対するご懸念や財政支援を求める声があることは承知しております。移行後の運用経費は、本来自治体が現行システムで負担する運用経費に相当するものであることなどを踏まえまして、各自治体が負担することが基本ではございます。
その上で、デジタル庁としても本年6月に決定した「自治体システムの標準化・ガバメントクラウド移行後の運用経費にかかる総合的な対策」に基づきまして対応を進めております。具体的には、当面の対策として各自治体が行う見積もり支援の強化や、クラウド利用料の更なる割引交渉などを行っております。特に見積もり精査支援の強化につきましては、都道府県とデジタル庁で連携をして、より手厚い市区町村への支援を推進しております。
また、システム運用管理の自動化や競争環境の改善に向けたシステム運用経費の見える化・分析など、構造的な要因に対する対策で経費の抑制を図ってまいります。
さらに、こうした対策を講じてもなお増加する運用経費に対する財政措置につきましては、様々な制約がある中で、デジタル庁としても知恵を絞り、関係省庁と連携して検討を進めているところです。今回の経済対策におきまして「移行後の運用経費の増加への対応を含めて、安定的な運用のために必要な措置を講じる」と決定したことも踏まえまして、予算編成において具体的な措置についての検討を加速してまいります。
高木佳保里 委員
よろしくお願いしたいと思います。標準化対応によって多大な財政的負担が生じる中で、このままでは自治体のDX予算が標準化システムの維持費だけに食いつぶされてしまう恐れがあります。本来目指すべき住民サービスやスマートシティの実現に予算が回らないということになりかねません。「システムを標準化した結果、自治体が貧乏になってしまった」「独自の住民サービスが低下した」と言われることがないようにお願いしたいと思います。
毎年の交付税措置だけではなく、実費に見合った補助金と直接的な財政支援の枠組みもしっかりとお考えいただきたいと思います。
もう少しこの点について伺います。現在、クラウド基盤や仮想化ソフトの市場では、外資系ベンダーによるライセンス体系の変更や大幅な値上げが相次いでいると聞いています。いわゆる「クラウドフレーション」ということで、自治体財政を圧迫する要因となっているとお聞きしていますが、国が主導するガバメントクラウドを利用する以上、一自治体の交渉力ではどうにもなりません。
政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)の基準を満たす事業者が限られている中で、特定ベンダーによる事実上のロックインや一方的な値上げに対して、国としてどう自治体をサポートしていくのか伺います。
奥田 審議官(デジタル庁)
ガバメントクラウドの調達にあたりましては、一度採用したクラウドサービスにロックインされることのないように、データが容易に移行できるツールや仕組みがあること、技術情報が公開されることを調達仕様書で求めるなど、特定クラウドから他のクラウドへの移行が困難とならないよう、いわゆるロックイン防止の対応を行っているところです。
また、ガバメントクラウドの利用料にかかる契約等につきましてはデジタル庁が一括して行っており、クラウドサービス事業者との交渉等は全てデジタル庁が行っております。
ご質問の一方的な値上げ対策としましては、クラウドを構成する各事業者とデジタル庁とのクラウドサービス基本契約におきまして、契約の変更等を行う場合には事前に協議を行うこととしており、クラウドサービス提供事業者が一方的に利用料を設定することはできないようにしているところです。 November 11, 2025
Microsoft が2026年からAI機能を無料に…みたいなポストがバズっているけど、面倒くさそうだからポストにぶらさげないけど、色々と間違ってると思うんだよなぁ。それでバズっちゃってるけど、Xってそんなもんだよね。自分の全く知らない領域でも同じような感じになってるんだろうね。情報は疑わねば。 November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。