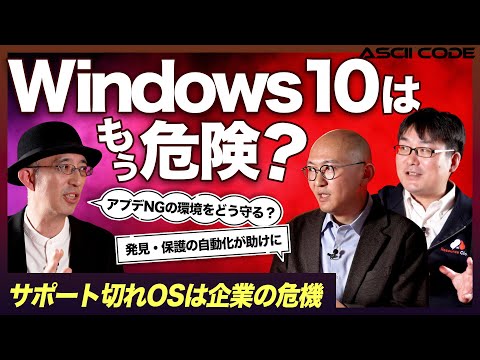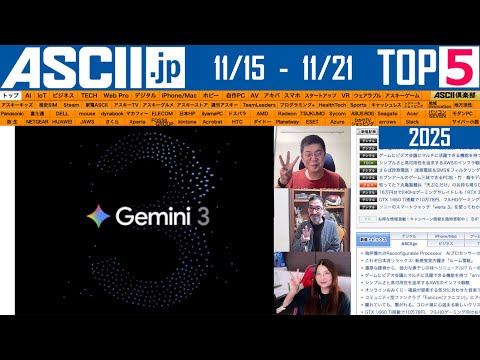セキュリティ
0post
2025.11.27 21:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
アサヒさんのランサム事案の記者会見(QA含む約2時間)からセキュリティクラスタ的に気になるであろう箇所をピックしました。以下16項目でまとめています。
・2025年9月29日(月)午前7時頃システム障害が発生し被害確認。詳細な日時は未特定だが約10日ほど前に同社グループ内の拠点にあるNW機器を経由し侵入。その後主要なDCに入り込みパスワードの脆弱性を突いて管理者権限を奪取し移動を行い、主に業務時間外に複数サーバに偵察侵入し、アクセス権認証サーバからランサムウェアが一斉実行され起動中のサーバやパソコンが暗号化された。
・被害発覚の10日ほど前から侵入されていた可能性があるが、その間は導入していたEDRでは検知できなかった。攻撃が高度で巧妙であったため。EDRのレベルをより上げる課題がある。強化して監視の仕組みも見直す。
・侵入経路はNW機器。VPN機器かどうかはセキュリティの都合から明言出来ないが世間の想像とそう違いはないと思います、ということで留めたい。入口になり得る"脆弱性"の改善は完了済み(※この"脆弱性"という言葉は社長発言だが狭義の既知脆弱性=CVEという意味では使ってなさそう)。VPN機器は存在していたが対応過程で廃止済み。
・被害が拡大しないよう安全性を確保しながら慎重に復旧を進めたため時間を要した。バックアップデータは取得しておりそれが生きていたことは幸いだった。バックアップは複数媒体で取得していた。大部分が健全な状態で保たれていた。
・明確な個人情報の漏洩は、従業員に貸与したPCの情報を確認しているが、システムからのデータ漏洩は未確認で可能性として考えている。
・社員の個人貸与PCに情報を残すことは許可しておらずクラウド保存をポリシーで定めていたが、一時的に保管していた個人の情報が残っておりそのタイミングで攻撃がきた。
・工場現場を動かすOT領域は一切影響を受けておらず無傷で、工場は通常稼働ができる状態だった。出荷関係のシステム被害により作っても持って行き先がないので製造に結果的に影響が出た。システムを使わないExcelなどで人力での出荷で対応していた。
・NISTフレームワークに沿った成熟度診断は実施しており一定以上のアセスメントが出来ていたため十分な対策を保持していると考えていた。外部のホワイトハッカーによる模擬攻撃も実施してリスク対処をしていたので、必要かつ十分なセキュリティ対策は取ってたと判断していた。しかし今回の攻撃はそれを超える高度で巧妙なものだった。
・被害範囲は主にDC内のサーバとそこから繋がってるパソコン。端末台数は37台。サーバ台数は明言できない。
・攻撃者に対する身代金は支払っていない。攻撃者と接触もしていない。脅迫も請求も直接は受けてない。
・身代金支払い要求への対応については障害早期では当然考えたが、バックアップあり自力復旧ができること、支払っても復旧できない事例があること、支払いが漏れた場合他の攻撃者からも狙われるリスクがあるため、慎重に捉えていた。反社会勢力への支払いのぜひもその前段階から相当ネガティブな懸念としてあった。復号キーがきたとしても復元にすごく時間がかかるという認識もしたので要求がきてもおそらく支払ってない。
・現場対応は非常に負担が大きく長時間労働等を懸念していた。リーダとして社員の健康が一番大事で命を削ってまで対応しなくて良いということをトップから繰り返し全社発信していた。対応を支援してくれた外部ベンダにも伝えていた。
・自然災害含む経営リスクに関して10個のリスクを定めてサイバーリスクも含めて十分な対策を取っていたと思っていたがより高度化しないといけない教訓となった。他のリスク項目も対策を見直す。
・他社には、経験からの教訓として、全体を広く見て対策を最新に保つことの必要性を伝えたい。結果的に全体として脆弱性を見れてなかったので、ないと思ったところにあったので侵入されたし、対策も最新、最強でなかったので障害が発生したので、それを裏返ししてほしい。
・経営者はテクノロジーやITに興味を持ってるというだけでは済まない。全てに気を配り対策に踏み込めるようなところまで入っていくべきということを実感した。知見を高めガバナンスに活かしていくべき。
・セキュリティの都合で開示できない情報は多々あるが、社会のために情報をより公開すべきというのは認識しており状況が整ったら検討したい。
記者会見動画リンク
https://t.co/2bG06AK1pH November 11, 2025
75RP
.
最近は
🌱の値段・大手の対応・詐欺とか…🤷🏾♂️🤦🏻♂️
って感じ
Chromeはセキュリティ・値段・質
何一つ劣らない自信とプライド持ってやってます
🎁でお渡しした方も
大手から乗り換えてくれたり有難いです🙂↕️
ぜひ当選できるように企画アピール待ってます🤝
https://t.co/PtycRCi418 https://t.co/2cxHBHJ5qm November 11, 2025
2RP
◤◢◤◢◤◢◤◢ @Immutable News ◢◤◢◤◢◤◢
「Immutable」って何だろう?Web3ゲーム時代の
次世代プラットフォームを分かりやすく解説!
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢
最近、海外のゲーム・クリプト界隈でよく名前が出てくるのが #Immutable(イミュータブル)というWeb3ゲームプラットフォームです。そこでチビクロTVがImmutableの概要とメリットを分かりやすく解説します!
1️⃣Immutableは「ゲーム専用の高速道路」!
まず押さえておきたいのは「Immutable」という名前が3つの意味で使われることです。ひとつは会社名としてのImmutable、もうひとつはその企業が運営するブロックチェーン(レイヤー2チェーン)としてのImmutable、そしてそこで使われる「IMXトークン」です。大枠としては「Web3ゲームに特化したインフラ」をまとめてImmutableと呼んでいると考えて問題ありません。
ImmutableはEthereum(イーサリアム)という大型ブロックチェーンの上に「ゲームに特化したレイヤー2」と呼ばれる仕組みを構築しています。レイヤー2というのは簡単に言うと「本線(Ethereum)の横に並ぶバイパス」のような存在です。Ethereum本体はセキュリティが高い一方で、取引が集中すると手数料が高くなり、処理が詰まりやすいという弱点があります。そこでゲームやNFTの取引をレイヤー2で処理して、まとめてEthereumに最終記録することで、速さと安さを両立させようという発想です。
例えば通勤ラッシュ時の一般道路がEthereum本体だとすると、Immutableは「ゲームユーザー専用の高速道路」を別に用意しているイメージです。みんなが同じ道路を使っていると渋滞しますが「ゲーム専用レーン」があればスムーズに流れますよね。Immutableはこの「ゲーム専用レーン」を世界中のWeb3ゲーム向けに提供しているようなものです。
もともとImmutableは「Immutable X」というNFT特化レイヤー2で知られていましたが、現在はPolygonの技術を取り入れた「Immutable zkEVM」という新しいチェーンを展開し、今後はこれらを統合した「Immutable Chain」として一本化していく構想を持っています。技術的な細かい話は抜きにすると「より速く、より安く、より開発しやすいゲーム向けチェーンにアップグレードしている途中」と理解しておけば十分です。
この上で動くのが「IMXトークン」です。IMXは、Immutableのエコシステムで手数料の支払いに使われたり、ステーキングやガバナンス(プロジェクトの方針を投票で決める仕組み)の用途を持つトークンとして設計されています。いわば、Immutableという国の中で流通するガソリンやポイントのような立ち位置で、エコシステム全体の成長とともに注目されています。
🧵以下、スレッドに続く👇 November 11, 2025
2RP
【Chromebook しりとりゲーム】
Chromebook(クロームブック)
→クラウド環境だから、データ紛失の心配が少ない
→いつでも軽い
→移行が簡単で、すぐに利用できるのが嬉しい
→いつでも安心できるセキュリティ
次は「い」から、対よろです。 November 11, 2025
1RP
まとめありがたい
この話を見ると、かなり力入れてセキュリティ対策やってたと思うけど、それでも最終的に暗号化まで行ってしまったので、本当にどういう攻撃があったんだろう https://t.co/uuLix0WTdf November 11, 2025
1RP
中抜き・ピンハネ悪質ランキング(16位〜30位)
16位 ベネッセコーポレーション(子育て支援・教育補助金委託)
推定中抜き額:約70億円(2020〜2025年、総受注中25%再委託)
問題点:こども家庭庁経由の育児支援システムで、外部NPOへ多重下請け。データ管理の不備がプライバシー漏洩を招き、補助金の効果測定が不透明。X上で「子育て支援の名の下に利益優先」と批判。
17位 倭国政策投資銀行(JIP)関連基金(地方創生補助金)
推定中抜き額:約60億円(2022〜2025年、基金総額中10%マージン)
問題点:地方交付金の一部がJIP経由でコンサル企業に再委託され、イベント経費に充当。成果報告の曖昧さが会計検査院で指摘され、地方経済活性化の名目が形骸化。
18位 NTTデータ(デジタル庁マイナンバー関連業務)
推定中抜き額:約50億円(2023〜2025年、総委託中20%外注)
問題点:マイナンバーシステム構築で子会社・下請けへ5次下請け。セキュリティ脆弱性が露呈し、税金の無駄遣いが国会で追及。デジタル化推進の遅延を助長。
19位 倭国ハム(外国人技能実習生支援補助金)
推定中抜き額:約45億円(2020〜2025年、研修プログラム中30%手数料)
問題点:技能実習生受け入れで仲介業者経由の補助金が中抜きされ、労働者への賃金配分が低迷。X上で「移民政策の闇」として、搾取構造が非難。
20位 電通ライブ(イベント運営委託、持続化給付金関連)
推定中抜き額:約40億円(2020〜2022年、電通グループ内再委託分)
問題点:給付金申請支援イベントで印刷・外注を大倭国印刷等へ丸投げ。利益循環が「グループ内中抜き」の典型例として、経産省検討会で規制強化の対象に。
21位 サービスデザイン推進協議会(持続化給付金元請け)
推定中抜き額:約35億円(2020〜2021年、総769億円中5%管理費)
問題点:電通OB主導の一般社団法人として巨額受注後、再委託連鎖。電通への97%丸投げが「トンネル団体」の象徴となり、野党から透明性欠如を批判。
22位 倭国熊森協会(野生動物対策補助金)
推定中抜き額:約30億円(2023〜2025年、クマ対策基金中15%運営費)
問題点:環境省補助金で捕獲代替策を提言するも、NPO経由の委託で中抜き。X上で「熊支援の名の下に公金チューチュー」と揶揄され、効果の検証不備。
23位 ハラール認証関連企業(食品補助金)
推定中抜き額:約25億円(2022〜2025年、輸出促進補助中20%認証手数料)
問題点:農林水産省補助金でハラール認証を推進するも、認証業者がマージンを過剰取得。国内需要の歪曲がXで議論され、文化政策の補助金依存を露呈。
24位 地方自治体コンサルタント集団(地方交付金事業)
推定中抜き額:約20億円(2024〜2025年、総交付金中10%コンサル費)
問題点:片山さつき担当相の租税特別措置・補助金見直し対象で、イベント・旅費に充当。SNS意見募集で「自己満足事業」との声が相次ぎ、無駄遣いの温床。
25位 SES企業連合(IT補助金・デジタル人材支援)
推定中抜き額:約18億円(2023〜2025年、経産省委託中25%ピラミッド手数料)
問題点:デジタル庁のIT遅れ是正事業で、多層下請け構造がGDP重しに。売り手市場の悪用で価格つり上げがReVerve Consulting報告で指摘。
26位 太陽光発電関連NPO(再エネ補助金)
推定中抜き額:約15億円(2022〜2025年、NEDO基金中12%運営マージン)
問題点:メガソーラー事業で失敗プロジェクト続きも補助継続。X上で「再エネマフィア」との批判が高まり、環境省の無駄金流用が会計検査院で問題化。
27位 NHK関連委託企業(放送補助金外注)
推定中抜き額:約12億円(2020〜2025年、受信料依存分中10%下請け)
問題点:NHKの補助金・委託で広告代理店経由の多重外注。公共放送の透明性欠如がXで炎上し、片山担当相の見直し対象に。
28位 外国人実習生仲介業者(技能実習補助金)
推定中抜き額:約10億円(2021〜2025年、厚労省補助中30%手数料)
問題点:ベトナム人実習生受け入れで時給中抜きが95%超。X上で「徴兵逃れの搾取」との投稿が散見され、人権侵害の補助金依存構造。
29位 ガソリン補助金元売り企業(燃料油価格激変緩和対策)
推定中抜き額:約8億円(2024〜2025年、総補助中5%事後精算マージン)
問題点:資源エネルギー庁のモニタリング不備で価格転嫁が不透明。参院経産委員会で村田きょうこ議員が「中抜き疑惑」を追及、国民負担増大。
30位 氷河期世代支援NPO(雇用補助金)
推定中抜き額:約5億円(2020〜2025年、厚労省委託中20%運営費)
問題点:支援事業で外注連鎖が氷河期世代の不満を助長。note記事で「見えない税金」として描かれ、成果の不在がX上で「支援の闇」と非難 November 11, 2025
1RP
🏦 アメリカ第5位の銀行、U.S. Bancorp が Stellar $XLM 上でステーブルコインをテスト
U.S. Bancorp - 米国で5番目に大きな銀行で、AUM 6710億ドル - が、現在 Stellar $XLM ブロックチェーン上で独自のステーブルコインをテスト中 🚀 。
この動きにより、同銀行は Bank of America や Citi などの他の主要機関と並び、USD および Treasury 裏付けのデジタル資産にますます深く参入するようになりました 💵。
🔐 なぜ Stellar か?
セキュリティとトランザクション制御が、同銀行の決定において主要な役割を果たしました。
エンタープライズイノベーションの上級副社長である Mike Villano は、Stellar の以下の能力を強調しました:
🔒 資産の凍結
↩️ トランザクションの取り消し
🧩 組み込みのコンプライアンス層の提供(KYC、監督)
これらの機能により、Stellar は規制された銀行環境に適した強力な選択肢となります。
💼 先月、U.S. Bank は以下のことに焦点を当てた Digital Assets Division を立ち上げました:
➖ステーブルコインの発行
➖暗号資産のカストディ
➖資産のトークン化
➖デジタルマネーの移動
「クライアントは、デジタル資産が資金の安全な移動、預金の保管、トークン化された資産の使用にどのように役立つかを理解したいと考えています」と、Chief Digital Officer の Dominic Venturo は述べました。
🌐 Stellar の信頼性:
このネットワークは10年間99.99%の稼働率を維持しており、Taurus、Franklin Templeton、WisdomTree、Circle などの企業によって使用されています ⚡️。
🔗 #Stellar #Blockchain #XLM #Crypto #DeFi November 11, 2025
1RP
【ノートンストア】
勝手に引き落とし!解約できない場合の自動延長の停止・返金方法を解説
このサイトマジで助かった。
セキュリティソフトの自動引き落としがライセンス更新日よりずっと前にされてて、新しい製品を買ったので返金して貰うのに苦労してたら無事に完了。感謝 https://t.co/R5lmqvKPUJ November 11, 2025
@9oo_chon えええそうなん!?ドストカムバときに有料の契約したから大丈夫やろと思ってたんやけど有料の方が弾かれるとかそんなん🫠そのときは無料のに繋ぐ感じ??セキュリティとか怖くない!?(色々聞いてごめん) November 11, 2025
「今回のビットコインの半減期バブルは本当に終わったのか?」投資家が今知るべき真相
「今回のビットコインの半減期バブルは本当に終わってしまったのか?」多くの投資家が抱えるこの疑問に対し、本記事では過去の半減期サイクルとの比較から、ビットコイン現物ETF導入後の市場構造変化、グローバルマクロ経済の不確実性、そしてマイナーの動向に至るまで、多角的な視点から徹底的に分析します。短期的な価格変動に一喜一憂するのではなく、今後のビットコイン価格を左右する機関投資家の継続的な需要や金融政策の転換点、テクノロジーの進化といった重要要因を深く理解することで、あなたはビットコイン市場の「真相」を掴み、冷静かつ戦略的な投資判断を下すための知識と洞察を得られるでしょう。結論として、市場は単純な「バブルの終焉」ではなく、より複雑で新たなフェーズへと移行している可能性が高く、この変化に適応するための具体的な投資戦略を提示します。
1. 今回のビットコインの半減期バブルは本当に終わったのか
2024年4月に4回目の半減期を迎えたビットコインは、多くの投資家の間で「半減期バブル」への期待を大きく高めました。しかし、半減期後の価格動向は、過去のサイクルとは異なる様相を呈しており、「今回のビットコインの半減期バブルは本当に終わったのか?」という疑問が、市場全体を覆っています。この疑問は、特に過去の半減期後の劇的な価格上昇を経験してきた投資家にとって、非常に深刻なものです。本章では、この問いに対し、過去のデータと現在の市場環境を詳細に比較し、投資家心理の深層を探ることで、その真相に迫ります。
1.1 過去の半減期サイクルと現在の状況を比較する
ビットコインの半減期は、約4年ごとに新規供給量が半減するイベントであり、歴史的にその後の価格上昇を促す主要な要因とされてきました。過去3回の半減期後のビットコイン価格は、いずれも数ヶ月から1年半程度の期間を経て、大幅な上昇を経験し、史上最高値を更新してきました。
以下に、過去の半減期とその後の価格動向の概要を示します。
半減期日付半減期直後の価格その後の最高値最高値到達までの期間上昇率(直後価格比)1回目2012年11月28日約12ドル約1,150ドル約1年約9,500%2回目2016年7月9日約650ドル約19,783ドル約1年半約2,900%3回目2020年5月11日約8,600ドル約69,000ドル約1年半約700%
しかし、今回の2024年4月の半減期は、過去とはいくつかの点で大きく異なる特徴を持っています。最も顕著なのは、半減期を迎える前にすでにビットコインが史上最高値を更新していた点です。これは、2024年1月に米国で承認されたビットコイン現物ETFの導入による機関投資家からの大規模な資金流入が、半減期前の価格を押し上げたためと考えられます。過去のサイクルでは、半減期後に供給が絞られ、需要が徐々に高まることで価格が上昇するというパターンが一般的でしたが、今回は半減期前からすでに需要主導の価格上昇が起こっていたと言えるでしょう。
このため、多くの市場参加者が期待していたような「半減期後の直線的な価格上昇」がすぐに現れないことに、一部の投資家は失望感を抱いています。過去のパターンがそのまま当てはまらない可能性を考慮し、現在の市場環境をより多角的に分析する必要があります。
1.2 市場心理の変化と投資家の期待値
ビットコイン市場における投資家の心理は、価格変動に大きな影響を与えます。過去の半減期サイクルでは、半減期が近づくにつれて「供給が減る」というシンプルなロジックから、価格上昇への期待が高まり、「今買わないと乗り遅れる」というFOMO(Fear Of Missing Out)心理が市場を牽引してきました。しかし、今回のサイクルでは、現物ETFの承認という歴史的なイベントが半減期に先行したことで、市場心理はより複雑になっています。
半減期前に史上最高値を更新したことで、一部の投資家は「すでに半減期の効果は織り込み済みである」と判断し、「Buy the rumor, Sell the news(噂で買って、ニュースで売る)」という行動パターンが見られました。これにより、半減期直後には、期待感からの買いが一段落し、利益確定売りが優勢となる局面も発生しました。特に、短期的な利益を求める個人投資家の間では、期待値と現実のギャップから、失望感が広がりやすい状況です。
一方で、機関投資家はより長期的な視点でビットコインを評価しており、現物ETFを通じた着実な需要は継続しています。彼らは半減期後の供給減少を長期的な価格上昇要因と捉えつつも、グローバルマクロ経済の動向や金融政策など、より広範な要因を考慮に入れた上で投資判断を行っています。したがって、市場全体としては、過去のような単純な「バブル」の再来を期待する心理から、より成熟した視点へと変化していると言えるでしょう。
このような市場心理の変化は、価格のボラティリティを高めると同時に、投資家がより冷静かつ戦略的な判断を下す必要性を高めています。半減期後のビットコイン価格が期待通りに推移しない背景には、こうした投資家心理の複雑な変化も深く関わっているのです。
2. なぜビットコイン価格は期待通りに上昇しないのか
2024年4月に実施されたビットコインの半減期は、過去のサイクルと同様に価格上昇への大きな期待を集めました。しかし、これまでのところ、市場は投資家の期待に応えるような爆発的な上昇を見せていません。この背景には、従来の半減期サイクルにはなかった新たな市場構造の変化や、グローバルな経済状況、そしてビットコインの供給サイドに起因する要因が複雑に絡み合っています。ここでは、なぜビットコイン価格が期待通りに上昇しないのか、その多角的な理由を深掘りします。
2.1 ビットコイン現物ETF導入後の市場構造変化
2024年1月に米国でビットコイン現物ETFが承認されたことは、ビットコイン市場に歴史的な転換点をもたらしました。これにより、機関投資家や従来の証券口座を持つ個人投資家が、より手軽かつ規制された環境でビットコインにアクセスできるようになったのです。しかし、この画期的な出来事が必ずしも価格の継続的な上昇に直結しなかったのには、いくつかの理由があります。
まず、ETF承認というビッグニュースが、一部の投資家にとっては「材料出尽くし」と受け止められ、承認後に利益確定売りを誘発する「Sell the News(ニュースで売る)」現象が見られました。また、新規に流入した資金が期待されたほど価格を押し上げなかった背景には、グレースケール・ビットコイン・トラスト(GBTC)からの大規模な資金流出が大きく影響しています。GBTCはETF転換後、高額な手数料やロックアップ期間の終了により、多くの投資家がより手数料の低い新規ETFへの乗り換えや、単純な売却を進めました。このGBTCからの売り圧力が、新規ETFへの資金流入を相殺し、価格上昇の勢いを鈍らせたのです。
さらに、ETFの導入はビットコイン市場の参加者層を大きく変化させました。伝統的な金融市場のプレイヤーが参入したことで、ビットコインはよりグローバルなマクロ経済指標や金融政策、さらには他のリスク資産との相関性を高める傾向にあります。これは、クリプトネイティブな市場要因だけでなく、より広範な金融市場の動向がビットコイン価格に与える影響が強まったことを意味します。
市場特性ETF導入前ETF導入後主な参加者個人投資家、クリプトネイティブな機関伝統的機関投資家、個人投資家(証券口座経由)アクセス手段暗号資産取引所、信託商品(GBTCなど)証券口座(ETF)、暗号資産取引所市場の透明性比較的低い伝統金融市場と同程度の透明性価格決定要因クリプト市場内部要因が強いグローバルマクロ、伝統金融市場の影響増大投資層の広がり限定的大幅に拡大
2.2 グローバルマクロ経済の不確実性
ビットコインはしばしば「デジタルゴールド」と称され、インフレヘッジや安全資産としての役割が期待されます。しかし、現在のグローバルマクロ経済環境は、ビットコインを含むリスク資産全般にとって逆風となっています。
最も大きな要因の一つは、米国連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策です。高止まりするインフレを抑制するため、FRBは高金利政策を維持しており、利下げ開始時期の不透明感が市場に重くのしかかっています。高金利環境下では、リスク資産への投資妙味が薄れ、より安全な債券などに資金が流れやすくなります。また、利下げ期待が後退するたびに、株式市場を含むリスク資産全体が調整局面を迎えることが多く、ビットコインもその影響を強く受けています。
さらに、世界各地で続く地政学的リスクも無視できません。ウクライナ戦争や中東情勢の緊迫化など、国際的な不安定要因は投資家のリスクオフ心理を高め、安全資産への逃避を促します。このような状況下では、たとえビットコインが長期的な成長性を持つと期待されていても、短期的な価格変動リスクを嫌う投資家が増え、新規資金の流入が抑制されがちです。
加えて、世界経済の成長鈍化懸念もビットコイン価格に影響を与えています。主要国の経済指標が芳しくない場合、企業の業績悪化や消費の冷え込みが懸念され、リスク資産への投資意欲が減退します。ビットコインが伝統的な金融市場、特にテクノロジー株との相関性を高めている現状では、これらのマクロ経済要因がビットコイン価格を左右する重要な要素となっているのです。
2.3 マイナーの動向と供給圧力
ビットコインの半減期は、新規供給量を半分に削減することで、理論的には価格上昇に寄与すると考えられています。しかし、半減期直後には、ビットコインを採掘するマイナーの動向が短期的な価格に影響を与えることがあります。
半減期によってブロック報酬が半減すると、マイナーの収益性は大幅に低下します。特に、電力コストが高い地域で採掘を行う小規模なマイナーや、効率の悪い旧式の機器を使用しているマイナーは、収益性の悪化に直面し、事業継続が困難になる可能性があります。このような状況下で、マイナーは運営コストを賄うため、あるいは事業撤退に際して、保有しているビットコインを売却する動きを強めることがあります。これが短期的な売り圧力となり、価格上昇を抑制する要因となります。
また、半減期前に採掘機器への大規模な投資を行ったマイナーも、その投資回収を急ぐために、採掘したビットコインを市場で売却するインセンティブが働きます。新規供給量が減少する一方で、既存のマイナーからの売り圧力が一時的に高まることで、需給バランスが崩れ、価格が期待通りに上昇しない状況が生じやすいのです。
長期的に見れば、半減期を経て効率的で大規模なマイナーが生き残り、ハッシュレートが安定することで、ビットコインネットワークの健全性は保たれます。しかし、半減期直後の数ヶ月間は、マイナーの財務状況や戦略的な売却が市場に与える影響は無視できないため、その動向を注意深く見守る必要があります。
3. 今後のビットコイン価格を左右する重要要因
ビットコインの価格動向は、単一の要因で決まるものではありません。半減期による供給量の変化だけでなく、より広範な市場環境、金融政策、技術的な進歩、そして規制の動向が複雑に絡み合って形成されます。ここでは、今後のビットコイン価格を左右する特に重要な要素を詳細に解説します。
3.1 機関投資家の継続的な需要
2024年1月に米国で承認されたビットコイン現物ETFは、機関投資家がビットコイン市場へ参入する道を大きく開きました。ブラックロックやフィデリティといった世界的な大手資産運用会社が提供するこれらのETFは、従来の証券口座を通じてビットコインへの投資を可能にし、これまでアクセスが困難だった層からの資金流入を促しています。
今後の価格を左右する上で最も重要なのは、この機関投資家からの需要が一時的なものに終わるのか、それとも長期的に継続するのかという点です。機関投資家は、短期的な投機目的だけでなく、長期的な資産配分、インフレヘッジ、そしてポートフォリオの分散化といった目的でビットコインを組み入れる傾向があります。彼らの継続的な資金流入は、市場の流動性を高めるとともに、供給量を吸収し、価格を下支えする重要な要因となるでしょう。
ETFへの資金流入データは日々注目されており、その推移が市場のセンチメントに大きな影響を与えます。もし資金流入が鈍化、あるいは流出に転じるようであれば、価格への下押し圧力となる可能性もありますが、現状では長期的な視点での需要は根強く、ビットコインをデジタルゴールドとしての地位に押し上げる原動力となり得ます。
3.2 金融政策の転換点と市場への影響
グローバルなマクロ経済環境、特に主要中央銀行の金融政策は、ビットコインを含むリスク資産の価格に極めて大きな影響を与えます。中でも、米国連邦準備制度理事会(FRB)の金利政策は、ビットコイン市場の動向を左右する最も重要な要素の一つです。
FRBが利上げを継続する局面では、国債などの安全資産の利回りが上昇するため、リスク資産であるビットコインから資金が流出しやすくなります。逆に、FRBが利下げに転じ、市場に資金が供給される量的緩和(QE)の局面に入れば、リスクオンの動きが強まり、ビットコインへの資金流入が期待されます。
また、インフレ率の動向も重要です。インフレが高止まりすれば、FRBは金融引き締めを継続せざるを得なくなり、ビットコイン価格には逆風となります。しかし、ビットコインが「デジタルゴールド」としてインフレヘッジの役割を果たすという見方もあり、特定の状況下ではインフレ高進が買い材料となる可能性も秘めています。
以下の表は、主要な金融政策の要素とビットコイン価格への一般的な影響を示しています。
金融政策の要素ビットコイン価格への一般的な影響金利引き上げ(利上げ)安全資産の魅力が増し、リスク資産から資金が流出しやすい。価格にはマイナスに作用。金利引き下げ(利下げ)リスク資産への投資意欲が高まり、資金が流入しやすい。価格にはプラスに作用。量的引き締め(QT)市場の流動性が低下し、リスク資産にはマイナスに作用。量的緩和(QE)市場に資金が供給され、リスク資産にはプラスに作用。高インフレ率金融引き締めを促す要因となり、価格にはマイナスに作用する可能性。ただし、インフレヘッジとしての需要が高まる場合もある。
3.3 テクノロジーの進化と規制動向
ビットコインの長期的な価値と普及は、その基盤となるテクノロジーの進化と、それを囲む各国の規制環境によって大きく左右されます。
3.3.1 テクノロジーの進化
ビットコインネットワーク自体のスケーラビリティ(処理能力)や利便性の向上は、より広範な採用を促す上で不可欠です。例えば、ライトニングネットワークのようなセカンドレイヤーソリューションの普及は、ビットコインをより高速かつ低コストで決済に利用できるようにし、その実用性を高めます。セキュリティの維持や、ウォレット技術の進化によるユーザーエクスペリエンスの改善も、ビットコインが長期的に成長するための重要な要素です。
また、ビットコインのマイニングにおけるエネルギー消費の問題、いわゆるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点も無視できません。再生可能エネルギーの利用推進など、環境負荷の低減に向けた取り組みが進むことは、持続可能性を重視する機関投資家からの評価を高め、より多くの資金流入を促す要因となります。
3.3.2 規制動向
世界各国における仮想通貨の規制の明確化は、機関投資家や企業が安心して市場に参入するための重要なステップです。曖昧な規制環境は、法的リスクを懸念する投資家にとって参入障壁となりますが、明確なルールが整備されれば、市場の透明性と信頼性が向上し、新たな資金流入を呼び込む可能性があります。
特に注目されるのは、欧州連合(EU)が導入したMiCA(欧州連合の暗号資産市場規制)です。これは世界で最も包括的な暗号資産規制の一つであり、その影響はEU域内にとどまらず、グローバルな規制動向に影響を与える可能性があります。米国においても、議会や証券取引委員会(SEC)による規制の枠組み作りが進行しており、その方向性がビットコイン市場に大きな影響を与えるでしょう。
さらに、各国の中央銀行が開発を進めるCBDC(中央銀行デジタル通貨)の動向も無視できません。CBDCは、ビットコインのような分散型デジタル通貨とは異なる性質を持つものの、デジタル決済の普及という点でビットコインとの競争関係や共存の可能性を生み出すことになります。規制当局がビットコインをどのように位置づけ、どのように統合していくかが、今後の価格形成において重要な要素となります。
4. 投資家が知るべきビットコイン市場の「真相」
「今回のビットコインの半減期バブルは本当に終わったのか」という問いに対し、投資家が最も知るべきは、市場が語る「表面的な物語」と、その奥に潜む「本質的な現実」のギャップです。感情的な判断に流されず、冷静な分析に基づいた視点を持つことが、この変動の激しい市場で成功するための鍵となります。
4.1 バブルの定義とその終焉を判断する基準
ビットコイン市場を語る上で「バブル」という言葉は頻繁に登場します。しかし、そもそもバブルとは何であり、その終焉をどのように判断すべきなのでしょうか。まずはその定義と、ビットコイン市場に適用する際の注意点を見ていきましょう。
一般的に、バブルとは、資産の価格がその本質的な価値(ファンダメンタルズ)から大きく乖離し、投機的な熱狂によって異常な高騰を遂げる現象を指します。歴史上、17世紀の「チューリップ・バブル」や2000年代初頭の「ITバブル」など、多くのバブルとその崩壊が記録されてきました。ビットコインもまた、2017年末や2021年の強気相場において、一部から「バブル」と称されることがありました。
では、ビットコイン市場におけるバブルの終焉を判断する具体的な基準は何でしょうか。以下の要素が複合的に作用することで、バブルの終焉が示唆されることがあります。
判断基準ビットコイン市場での特徴と注意点価格の大幅な下落ピークから50%以上の急落は一般的なバブル崩壊の兆候とされる。しかし、ビットコインは元来ボラティリティが高く、一時的な大幅下落が必ずしもバブル終焉を意味しない場合もある。市場心理の転換楽観的な「FOMO(乗り遅れることへの恐怖)」から、悲観的な「FUD(恐怖、不確実性、疑念)」への急速な変化。新規参入者の激減や、既存投資家による投げ売りが顕著になる。出来高の減少市場の活気が失われ、取引量が著しく減少する。これは、投機的な資金が市場から流出し、関心が薄れていることを示す。ファンダメンタルズの停滞ビットコインネットワークの利用率低下、開発活動の停滞、ハッシュレートの減少など、基盤技術やエコシステムの成長が鈍化する。メディアの論調変化肯定的な報道や楽観的な予測が減少し、批判的・否定的な報道が増える。市場の熱狂が冷め、冷静な(あるいは悲観的な)視点が増す。
ビットコインの場合、その非中央集権性や発行上限枚数といった特性から、伝統的な資産のバブルとは異なる側面も持ちます。一時的な価格調整を「バブル崩壊」と早計に判断せず、より長期的な視点と複数の指標を組み合わせた総合的な判断が不可欠です。
4.2 短期的な変動と長期的な成長性
ビットコイン市場は、日々のニュースやマクロ経済の動向に敏感に反応し、短期的な価格変動が非常に大きいという特徴があります。しかし、これらの短期的なノイズに惑わされず、その裏にある長期的な成長性を見極めることが、賢明な投資家には求められます。
短期的な価格変動の主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。
グローバルマクロ経済指標: 各国の中央銀行による金融政策(金利決定、量的緩和・引き締め)、インフレ率、雇用統計などの発表は、リスク資産全般に影響を与え、ビットコインも例外ではありません。
地政学的リスク: 戦争や紛争、国際的な緊張の高まりは、安全資産への資金移動を促し、ビットコインの価格にも影響を与えることがあります。
機関投資家や大口投資家の動向: 大手機関投資家による大量の売買や、ビットコイン現物ETFへの資金流入・流出は、市場に大きなインパクトを与えます。
規制動向: 各国の政府や規制当局による仮想通貨に関する新たな規制の発表は、市場のセンチメントを大きく左右します。
技術的なニュースやセキュリティ問題: ネットワークのアップグレードや、取引所のハッキングなどのニュースも短期的な価格変動要因となります。
一方で、ビットコインの長期的な成長性を支える本質的な価値は、これらの短期的な変動要因とは独立して存在します。
希少性と供給上限: 2100万枚という発行上限と、半減期による供給量の減少は、ビットコインを「デジタルゴールド」としての価値を高めています。
ネットワーク効果: ユーザー、開発者、企業、決済プロバイダーが増加するにつれて、ビットコインのネットワークはより堅牢になり、その価値は指数関数的に向上します。
技術革新とエコシステムの拡大: ライトニングネットワークのようなスケーリングソリューションの進化や、DeFi(分散型金融)領域との連携強化は、ビットコインの利用可能性を広げます。
機関投資家の継続的な参入: ビットコイン現物ETFの承認は、伝統的な金融市場からの大規模な資金流入を可能にし、今後も機関投資家による需要は長期的な価格を支える要因となるでしょう。
グローバルな普及とインフレヘッジとしての需要: 新興国での金融インフラとしての利用拡大や、先進国におけるインフレヘッジとしての認識の高まりは、長期的な需要を喚起します。
「バブルが終わったのか」という問いに対する「真相」は、短期的な価格の上下動だけを見て判断するのではなく、ビットコインが持つ本質的な価値と、長期的な視点での成長ポテンシャルを総合的に評価することにあります。 半減期後の市場は、短期的な調整期間を経ながらも、これらの根源的な要因によって、今後もその価値を高めていく可能性を秘めていると言えるでしょう。
5. 半減期後のビットコイン投資戦略
ビットコインの半減期は、過去のデータからは価格上昇の触媒として機能してきた側面があるものの、今回のサイクルでは市場構造の変化やグローバルマクロ経済の不確実性が絡み合い、単純な価格上昇を期待することは難しくなっています。このような複雑な市場環境において、投資家は感情に流されず、自身の投資目標とリスク許容度に基づいた戦略を立てることが不可欠です。
5.1 リスクとリターンを考慮したポートフォリオ戦略
ビットコインは依然として高いボラティリティを持つ資産であり、大きなリターンを期待できる一方で、それに見合うリスクも存在します。半減期後の市場で賢く立ち回るためには、自身のポートフォリオ全体におけるビットコインの位置づけを明確にし、リスク管理を徹底することが重要です。
5.1.1 分散投資の原則とビットコインの組み入れ
「卵を一つのカゴに盛るな」という投資の格言は、ビットコイン投資においても当てはまります。ビットコインのみに全資産を集中させるのではなく、株式、債券、不動産、その他の暗号資産(アルトコイン)など、異なる資産クラスと組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを低減しつつ、安定したリターンを目指すことが可能です。ビットコインは高い成長性を期待できる「攻め」の資産として位置づけ、その配分は個人のリスク許容度に合わせて慎重に決定すべきです。
5.1.2 長期的な視点での積立投資(ドルコスト平均法)
市場の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことはビットコイン投資において特に重要です。ドルコスト平均法を用いた積立投資は、価格が高い時には少なく、価格が低い時には多く購入することになり、結果的に平均購入価格を平準化する効果が期待できます。これにより、市場のタイミングを計る難しさから解放され、感情的な売買を避けることができます。半減期後の価格が不透明な状況では、特に有効な戦略と言えるでしょう。
5.1.3 投資戦略のタイプ別アプローチ
ビットコイン投資には様々なアプローチがありますが、自身の投資目標、リスク許容度、利用可能な時間に応じて最適な戦略を選択することが重要です。以下に代表的な戦略とそれぞれの特徴を示します。
戦略タイプ特徴適した投資家主なリスク長期保有(HODL)価格の短期的な変動に左右されず、数年単位でビットコインを保有し続ける戦略。高いリスク許容度があり、市場分析に時間を割けないが、長期的な成長を信じる投資家。市場の長期的な下落トレンド、技術的な陳腐化。積立投資(ドルコスト平均法)定期的に一定額を投資し、購入価格を平均化することで、市場のタイミングを計るリスクを低減する戦略。初心者、市場のタイミングを気にせず時間分散して投資したい投資家。長期的な価格停滞、市場の継続的な下落。ポートフォリオ分散(アルトコイン含む)ビットコインだけでなく、他の有望なアルトコインや伝統資産を組み合わせ、リスクを分散しつつリターンを追求する戦略。リスクを抑えつつ、暗号資産市場全体の成長機会を捉えたい投資家。アルトコインのプロジェクト固有のリスク、市場全体の連動性。リバランス戦略定期的にポートフォリオの資産配分を見直し、当初設定した比率に戻すことで、リスクとリターンのバランスを維持する戦略。積極的なリスク管理を行いたい投資家、市場の変動を利用して利益を確保したい投資家。リバランス時の取引コスト、市場の急激な変動への対応の遅れ。
5.2 情報収集と冷静な判断の重要性
暗号資産市場は、ソーシャルメディアのトレンドやニュース、インフルエンサーの発言によって価格が大きく変動しやすい特性を持っています。半減期後の不確実性が高い時期においては、正確な情報に基づいた冷静な判断が、投資の成功を左右します。
5.2.1 信頼できる情報源の選定とファンダメンタルズ分析
インターネット上には玉石混交の情報が溢れています。投資判断を行う際には、金融庁などの公的機関の発表、信頼できる大手メディア、経済専門誌、あるいは主要な暗号資産分析企業のレポートなど、客観的で裏付けのある情報源を選定することが極めて重要です。また、ビットコインの価格は単なる需給だけでなく、その基盤技術の進化、ネットワークの利用状況、主要企業による採用動向、各国の規制状況といったファンダメンタルズ要因によっても大きく影響されます。これらの要素を定期的に分析し、ビットコインの長期的な価値を見極めることが肝要です。
5.2.2 感情的な売買の回避と自己規律
市場が急騰すると「乗り遅れてはいけない」というFOMO(Fear Of Missing Out)に駆られ、急落すると「これ以上損をしたくない」という恐怖からパニック売りをしてしまうことがあります。このような感情的な売買は、往々にして投資家にとって不利な結果を招きます。事前に設定した投資計画や損切りラインを厳守し、市場の喧騒から一歩引いて、冷静に状況を分析する自己規律を持つことが、半減期後のビットコイン投資を成功させる鍵となります。
例えば、金融庁のウェブサイトでは、暗号資産に関する注意喚起やリスク情報が提供されています。投資を検討する際は、こうした公的な情報を確認することが推奨されます。
6. まとめ
「今回のビットコインの半減期バブルは本当に終わったのか」という問いに対し、短期的な高揚感や急騰期待は一旦落ち着いたと結論づけることができます。過去の半減期サイクルとは異なり、ビットコイン現物ETFの導入による市場構造の変化、世界的なマクロ経済の不確実性、そしてマイナーの動向などが複雑に絡み合い、価格は期待通りに一直線には上昇していません。
しかし、これはビットコイン市場の「バブルの終焉」を意味するものではなく、むしろ「市場の成熟化」と捉えるべきです。機関投資家による継続的な需要、各国金融政策の転換点、そしてブロックチェーン技術の進化とそれに伴う新たなユースケースの創出は、中長期的なビットコインの価値を支える重要な要因として依然として存在します。
投資家は、短期的な価格変動に一喜一憂することなく、ビットコインの持つ本質的な価値と長期的な成長性に着目し、リスクとリターンを考慮したポートフォリオ戦略を立てることが肝要です。信頼できる情報源からの収集と冷静な判断が、半減期後のビットコイン投資で成功するための鍵となるでしょう。 November 11, 2025
@05yochimumu15 騒がしいの大歓迎だよ~🥰
ちびのり🐯好きなお菓子とかある!?(すでに貢ぐ気満々なやつ)
母兼マネージャー兼とぅめなんてちょー楽しそうじゃん😚❣️
TREASUREセキュリティはずっとやりたいと思ってる🥺将来の夢🥺ww November 11, 2025
朝日グループホールディングス、大規模ランサムウェア攻撃で191万件の個人情報流出か―2025年11月27日会見で明らかに|がらむまさら @LePandaIvre https://t.co/4T7Xx90CqC
気になったのでバチコーンと内容をまとめました。少し長いですが、社内ネットワークセキュリティが甘かったんだ残念って話。 November 11, 2025
説明会聴いたけど、現経営陣、流石やな
バッチリやん
てか、チューリンガム元代表の田中さんと、
チューリンガム・ラボ所長の船津さんがクシムに来て、
そのチューリンガム・ラボでやってたセキュリティをクシムラボでやるんやろ笑
面白くなってきた! https://t.co/5ZOCHTs5Vt https://t.co/sIaSuFfan1 November 11, 2025
わぁBlue Coatのgot spyware?Tシャツ出てる!あの頃のセキュリティ厨心くすぐられる〜羨ましいよぉ😂
got系 半袖Tシャツ Blue Coat 90s〜00sビンテージ XLサイズ
https://t.co/rKgd2UrqM2 November 11, 2025
話と関係ないんだけどサマソニでガンズ見たときライブ始まった瞬間にバケット自分のとこに飛んできて手にしたと思ったら群衆に飲み込まれて窒息しそうになったところをセキュリティのおっきい外国人さんに助けられた思い出 https://t.co/NpyMckgSjH November 11, 2025
2026年1月18日TalkingBOXにて高井ホアンさんとイベントに出演します。今回は防犯・防災・交通安全アニメの魅力を語るという限界にチャレンジするイベントになります。ネットセキュリティアニメや消費者問題アニメも語ります。 https://t.co/fUnaq8NJrD November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。