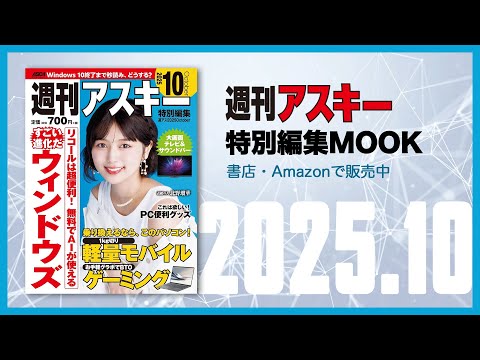クラウド
0post
2025.11.25 19:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
衝撃⚡️まじでヤバい💔
【渋谷発 次世代テック/エコシステム構築】
効率化の鬼&AI芸人で有名な大人気講師
モーリー氏@skillfreakdx
カスタマークラウドに特別枠で正式参画🚀
第2のビットバレー構想、いよいよ“人材集積フェーズ”へ ―
この最後の波に気付き乗れるか否か。
まもなく、倭国が返り咲く🇯🇵🌸‼️
https://t.co/zILvEtIfEm @PRTIMES_JP November 11, 2025
159RP
【DLsite】購入済みPCゲーム2万作品がスマホでプレイ可能に
https://t.co/np3xK14FFy
追加費用なし・インストール不要のクラウド方式で場所を選ばず楽しめる。期間限定キャンペーンは11月30日まで開催中。 https://t.co/ECQBlYTSvl November 11, 2025
28RP
Windows10から11へのアップデートで、リリース当初より愛用していたGoogle倭国語入力が絶望的なまでに変換能力を低下させ、あまりにも使い物にならなかったので、この一カ月でATOKとMS倭国語入力を使い比べてみた結果の寸評。
ATOK:現時点での変換能力は一番高いように感じるのだが、年間7200円支払うほどの性能差は感じられない。アホな変換は普通にしまくるので、値段相応に素晴らしく快適とは思わなかった。あとブラウザを強制終了が頻発するのは俺の個人環境だけかな?
MS倭国語入力:特別優秀だと思うことは無いのだが、無料と思えば十分な気もする。動作の重さを感じる瞬間が稀にあるが、気にならないレベル。ショートカット登録などインターフェイスのカスタマイズ余地がほぼ無いのが凄く困る。
Google倭国語:この前まではなんの不満もなかったのが、Windows11にした途端唐突に絶望的な変換をお出ししてくるようになり、最初は自分が脳の病気にでもなったのかとマジで心配になった。クリーンな再インストールしても無駄。キャラや作品名など様々な固有名詞が自動的にクラウド辞書として登録される機能はどの倭国語入力も備えているようだが、それに関してはGoogle倭国語入力がずば抜けて高い。それは今もそう。だが本当に変換能力が終わってる。そしてGoogle側にアップデートする気がほぼ無いのが絶望を加速させる。 November 11, 2025
7RP
Gemini3, Nano Banana Pro登場で, 先月時点で私がTBSの以下番組で「OpenAIは危うい.Googleが勝つ」としてたのが注目(特に投資家層?)されてるようです
実際は公には以下記事で2024年OpenAI絶頂期からずっとGoogle有利とみてます
長い(私のX史上最長)ですが根拠, OpenAI vs Googleの展望を書いてみます
先月のTBS動画:https://t.co/kgWcyTOTWK
2024年6月の記事:https://t.co/4HEhA4IJQa
参考のため、私がクローズドな投資家レクなどで使う資料で理解の助けになりそうなものも貼っておきます。
※以下はどちらかというと非研究者向けなので、研究的には「当たり前では」と思われることや、ちょっと省略しすぎな点もあります。
まず、現在の生成AI開発に関して、性能向上の根本原理、研究者のドグマ的なものは以下の二つです。基本的には現在のAI開発はこの二つを押さえれば大体の理解ができると思います。両者とも出てきたのは約5年前ですが、細かい技術の発展はあれど、大部分はこの説に則って発展しています。
①スケーリング則
https://t.co/WKl3kTzcX5
②SuttonのThe Bitter Lesson
https://t.co/esHtiJAcH9
①のスケーリング則は2020年に出てきた説で、AIの性能は1)学習データの量、2)学習の計算量(=GPUの投入量)、3)AIのモデルサイズ(ニューラルネットワークのパラメータ数)でほぼ決まってしまうという説です。この3つを「同時に」上げ続けることが重要なのですが、1と3はある程度研究者の方で任意に決められる一方、2のGPUはほぼお金の問題になります。よって、スケーリング則以降のAI開発は基本的にお金を持っている機関が有利という考えが固まりました。現在のChatGPTなどを含む主要な生成AIは一つ作るのに、少なく見積もってもスカイツリーを一本立てるくらい(数百億)、実際には研究の試行錯誤も含めると普通に数千億から数兆かかるくらいのコストがかかりますが、これの大部分はGPUなどの計算リソース調達になります。
②のThe Bitter Lessonは、研究というよりはRichard Suttonという研究者個人の考えなのですが、Suttonは現在のAI界の長老的な人物で、生成AI開発の主要技術(そして私の専門)でもある強化学習の事実上の祖かつ世界的な教科書(これは私達の翻訳書があるのでぜひ!)の執筆者、さらにわれわれの分野のノーベル賞に相当するチューリング賞の受賞者でもあるので、重みが違います。
これは端的にいうと、「歴史的に、AIの発展は、人間の細かい工夫よりも、ムーアの法則によって加速的に発展する計算機のハードの恩恵をフルに受けられるものの方がよい。つまりシンプルで汎用的なアルゴリズムを用い、計算機パワーに任せてAIを学習させた方が成功する。」ということを言っています。
①と②をまとめると、とにかく現状のAIの性能改善には、GPUのような計算リソースを膨大に動員しなければならない。逆に言えばそれだけの割と単純なことで性能上昇はある程度約束されるフェーズでもある、ということになります。
これはやや議論を単純化しすぎている部分があり、実際には各研究機関とも細かいノウハウなどを積み重ねていたり、後述のようにスケーリングが行き詰まることもあるのですが、それでも昨今のAI発展の大半はこれで説明できます。最近一般のニュースでもよく耳にするようになった異常とも言えるインフラ投資とAIバブル、NVIDIAの天下、半導体関連の輸出制限などの政治的事象も、大元を辿ればこれらの説に辿り着くと思います。
以下、この二つの説を前提に話を進めます。
公にはともかく私が個人的に「OpenAIではなくGoogleが最終的には有利」と判断したのはかなり昔で、2023年の夏時点です。2023年6月に、研究者界隈ではかなり話題になった、OpenAIのGPT-4に関するリーク怪文書騒動がありました。まだGoogleが初代Geminiすら出してなかった時期です。(この時期から生成AIを追っている人であれば、GPT-4のアーキテクチャがMoEであることが初めて明らかになったアレ、と言えば伝わるかと思います)
ChatGPTの登場からGPT-4と来てあれほどの性能(当時の感覚で言うと、ほぼ錬金術かオーパーツの類)を見せられた直後の数ヶ月は、さすがに生成AI開発に関する「OpenAIの秘伝のタレ説」を考えており、OpenAIの優位は揺らがないと考えていました。論文では公開されていない、既存研究から相当逸脱した特殊技術(=秘伝のタレ)がOpenAIにはあって、それが漏れない限りは他の機関がどれだけお金をかけようが、まず追いつくのは不可能だと思っていたのです。しかし、あのリーク文書の結論は、OpenAIに特別の技術があったわけではなく、あくまで既存技術の組み合わせとスケーリングでGPT-4は実現されており、特に秘伝のタレ的なものは存在しないというものでした。その後、2023年12月のGemini初代が微妙だったので、ちょっと揺らぐこともあったのですが、基本的には2023年から私の考えは「最終的にGoogleが勝つだろう」です。
つまり、「スケーリングに必要なお金を持っており、実際にそのAIスケーリングレースに参加する経営上の意思決定と、それを実行する研究者が存在する」という最重要の前提について、OpenAIとGoogleが両方とも同じであれば、勝負が着くのはそれ以外の要素が原因であり、Googleの方が多くの勝ちにつながる強みを持っているだろう、というのが私の見立てです。
次に、AI開発競争の性質についてです。
普通のITサービスは先行者有利なのですが、どうもAI開発競争については「先行者不利」となっている部分があります。先行者が頑張ってAIを開発しても、その優位性を保っている部分でAIから利益を得ることはほとんどの場合はできず、むしろ自分たちが発展させたAI技術により、後発事業者が追いついてきてユーザーが流出してしまうということがずっと起きているように思われます。
先ほどのスケーリング則により、最先端のAIというのはとても大きなニューラルネットワークの塊で、学習時のみならず、運用コストも膨大です。普通のITサービスは、一旦サービスが完成してしまえば、ユーザーが増えることによるコスト増加は大したことがないのですが、最先端の生成AIは単なる個別ユーザーの「ありがとうございます」「どういたしまして」というチャットですら、膨大な電力コストがかかる金食い虫です。3ドル払って1ドル稼ぐと揶揄されているように、基本的にはユーザーが増えれば増えるほど赤字です。「先端生成AIを開発し、純粋に生成AIを使ったプロダクトから利益を挙げ続ける」というのは、現状まず不可能です。仮に最先端のAIを提供している間に獲得したユーザーが固定ユーザーになってくれれば先行者有利の構図となり、その開発・運営コストも報われるのですが、現状の生成AIサービスを選ぶ基準は純粋に性能であるため、他の機関が性能で上回った瞬間に大きなユーザー流出が起きます。現状の生成AIサービスはSNSのように先行者のネットワーク効果が働かないため、常に膨大なコストをかけて性能向上レースをしなければユーザー維持ができません。しかも後発勢は、先行者が敷いた研究のレールに乗っかって低コストで追いつくことができます。
生成AI開発競争では以上の、
・スケーリング則などの存在により、基本的には札束戦争
・生成AIサービスは現状お金にならない
・生成AI開発の先行者有利は原則存在しない
と言う大前提を理解しておくと、読み解きやすいかと思います。
(繰り返しですがこれは一般向けの説明で、実際に現場で開発している開発者は、このような文章では表現できないほどの努力をしています。)
OpenAIが生成AI開発において(先週まで)リードを保っていた源泉となる強みは、とにかく以下に集約されると思います。
・スケーリングの重要性に最初に気付き、自己回帰型LLMという単なる「言語の穴埋め問題がとても上手なニューラルネットワーク」(GPTのこと)に兆レベルの予算と、数年という(AI界隈の基準では)気が遠くなるような時間を全ベットするという狂気を先行してやり、ノウハウ、人材の貯金があった
・極めてストーリー作りや世論形成がうまく、「もうすぐ人のすべての知的活動ができるAGIが実現する。それを実現する技術を持っているのはOpenAIのみである」という雰囲気作りをして投資を呼び込んだ
前者については、スケーリングと生成AIという、リソース投下が正義であるという同じ技術土俵で戦うことになる以上、後発でも同レベルかそれ以上の予算をかけられる機関が他にいれば、基本的には時間経過とともにOpenAIと他の機関の差は縮みます。後者については、OpenAIがリードしている分には正当化されますが、一度別の組織に捲られると、特に投資家層に対するストーリーの維持が難しくなります。
一方のGoogleの強みは以下だと思います。
・投資マネーに頼る必要なく、生成AI開発と応用アプリケーションの赤字があったとしても、別事業のキャッシュで相殺して半永久的に自走できる
・生成AIのインフラ(TPU、クラウド事業)からAI開発、AIを応用するアプリケーション、大量のユーザーまですべてのアセットがすでに揃っており、各段階から取れるデータを生かして生成AIの性能向上ができる他、生成AIという成果物から搾り取れる利益を最大化できる
これらの強みは、生成AIのブーム以前から、AIとは関係なく存在する構造的なものであり、単に時間経過だけでは縮まらないものです。序盤はノウハウ不足でOpenAIに遅れをとることはあっても、これは単に経験の蓄積の大小なので、Googleの一流開発者であれば、あとは時間の問題かと思います。
(Googleの強みは他にももっとあるのですが、流石に長くなりすぎるので省略)
まとめると、
生成AIの性能は、基本的にスケーリング則を背景にAI学習のリソース投下の量に依存するが、これは両者であまり差がつかない。OpenAIは先行者ではあったが、AI開発競争の性質上、先行者利益はほとんどない。OpenAIの強みは時間経過とともに薄れるものである一方、Googleの強みは時間経過で解消されないものである。OpenAIは自走できず、かつストーリーを維持しない限り、投資マネーを呼び込めないが、一度捲られるとそれは難しい。一方、GoogleはAIとは別事業のキャッシュで自走でき、OpenAIに一時的に負けても、長期戦でも問題がない。ということになります。
では、OpenAIの勝利条件があるとすれば、それは以下のようなものになると思います。
・OpenAIが本当に先行してAGI開発に成功してしまう。このAGIにより、研究開発や肉体労働も含むすべての人間の活動を、人間を上回る生産性で代替できるようになる。このAGIであらゆる労働を行なって収益をあげ、かつそれ以降のAIの開発もAGIが担うことにより、AIがAIを開発するループに入り、他の研究機関が原理的に追いつけなくなる(OpenAIに関する基本的なストーリーはこれ)
・AGIとまではいかなくとも人間の研究力を上回るAIを開発して、研究開発の進捗が著しく他の機関を上回るようになる
・ネットワーク効果があり先行者有利の生成AIサービスを作り、そこから得られる収益から自走してAGI開発まで持っていく
・奇跡的な生成AIの省リソース化に成功し、現在の生成AIサービスからも収益が得られるようになる
・生成AI・スケーリング則、あるいは深層学習とは別パラダイムのAI技術レースに持ち込み技術を独占する(これは現在のAI研究の前提が崩れ去るので、OpenAI vs Googleどころの話ではない)
・Anthropicのように特定領域特化AIを作り、利用料金の高さを正当化できる価値を提供する
最近のOpenAIのSora SNSや、検索AI、ブラウザ開発などに、この辺の勝利条件を意識したものは表れているのですが、今のところ成功はしていないのではないかと思います。省リソース化に関しては、多分頑張ってはいてたまに性能ナーフがあるのはこれの一環かもしれないです。とはいえ、原則性能の高さレースをやっている時にこれをやるのはちょっと無理。最後のやつは、これをやった瞬間にAGIを作れる唯一のヒーローOpenAIの物語が崩れるのでできないと思います。
最後に今回のGemini3.0やNano Banana Pro(実際には二つは独立のモデルではなく、Nano Bananaの方はGemini3.0の画像出力機能のようですが)に関して研究上重要だったことは、事前学習のスケーリングがまだ有効であることが明らかになったことだと思います。
ここまでひたすらスケーリングを強調してきてアレですが、実際には2024年後半ごろから、データの枯渇によるスケーリングの停滞が指摘されていること、また今年前半に出たスケーリングの集大成で最大規模のモデルと思われるGPT-4.5が失敗したことで、単純なスケーリングは成り立たなくなったとされていました。その一方で、
去年9月に登場したOpenAIのo1やDeepSeekによって、学習が終わった後の推論時スケーリング(生成AIが考える時間を長くする、AIの思考過程を長く出力する)が主流となっていたのが最近です。
OpenAIはそれでもGPT-5開発中に事前学習スケーリングを頑張ろうとしたらしいのですが、結局どれだけリソースを投下しても性能が伸びないラインがあり、諦めたという報告があります。今回のGemini3.0に関しては、関係者の発言を見る限り、この事前学習のスケーリングがまだ有効であり、OpenAIが直面したスケーリングの限界を突破する方法を発見していることを示唆しています。
これはもしかしたら、単なるお金をかけたスケーリングを超えて、Googleの技術上の「秘伝のタレ」になる可能性もあり、上記で書いた以上の強みを今回Googleが手にした可能性もあると考えています。
本当はもっと技術的に細かいことも書きたいのですが、基本的な考えは以上となります。色々と書いたものの、基本的には両者が競争してもらうことが一番技術発展につながるとは思います! November 11, 2025
7RP
【SPクラウド版メンテナンス終了のお知らせ】(2/2)
本件のお詫びとして、皆様に別途無償スタージュエル200個を配布しました。
この度はご迷惑をおかけし申し訳ございません。
詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
#クルスタ November 11, 2025
5RP
【 内部から狙われるという現実 】
■ 重要インフラや防衛産業では、外部からの攻撃だけでなく「内部者による情報流出」という見えにくいリスクが指摘されています。
重要な情報には、例えば次のようなものがあります。
・重要な設備情報
・運用データ
・設計図面
こうした情報が一度外に出てしまえば、後から完全に回収することはほとんど不可能です。
それでも倭国では、内部者リスクに一貫して対処する制度について、主要国と比べてなお課題が残ると指摘されています。
■ 米国や英国などの主要国では、防衛分野や重要インフラに携わる人材に対して、セキュリティ・クリアランス制度に基づく厳格な身辺調査が行われています。
退役軍人や元当局者が機密を持ち出した場合には、故意の漏えいだけでなく、重大な過失による漏えいでも重い刑罰が科される国もあります。
防衛関連企業の社員についても、法令や政府規則に基づき、アクセス権限の管理や持ち出し手順が詳細に定められている国が少なくありません。
■ 倭国でも、特定秘密保護法や経済安全保障推進法に加え、重要経済安保情報を対象とする新たなセキュリティ・クリアランス制度(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律)など、部分的な対策は整備されてきました。
経済安保分野では、政府が指定する「重要経済安保情報」について、適性評価に基づくアクセス管理や罰則を伴う枠組みの運用が始まっています。
防衛分野でも、防衛産業保全マニュアルや「装備品等秘密」など、契約と法令を組み合わせた産業保全制度の強化が進んでいます。
■ しかし、これらはいずれも「政府があらかじめ指定した情報」や「政府から企業に提供される秘密情報」の保護が中心です。
現実には、国が指定する前の段階から、次のような情報が外国政府やその関係機関の標的になっています。
・最先端の民生技術
・重要インフラ企業の運用データ
・研究開発段階の設計情報
そして、そうした情報の多くは、現行制度上、次のような要件を形式的には満たさず、法の網の目から漏れてしまうリスクが指摘されています。
・重要経済安保情報
・特定秘密
・営業秘密
■ たとえば、重要インフラの運用ログやシステム構成図、防衛関連の試作品情報が、内部者によって私物端末やクラウド経由で持ち出されるリスクが懸念されています。
こうした情報は、一件一件を見ると「単なる技術資料」「日常的な業務データ」に見えるかもしれません。
しかし、海外で長期的に収集・分析されれば、サイバー攻撃の精度向上や兵器システムの弱点把握に直結しかねません。
一度漏えいすれば「どこまで出回ったのか」を完全に把握することは難しく、長期にわたって倭国の安全保障や経済利益をむしばむ要因になります。
■ 現行法でも、窃盗や不正アクセス、不正競争防止法による営業秘密侵害などに該当すれば処罰は可能です。
しかし、形式上「営業秘密」に当たらない情報や、国家情報機関が関与する組織的な産業スパイ行為については、個々の行為を一般刑法でつまみ食い的に処理せざるを得ない場面が残ると指摘されています。
企業側も社内規程やセキュリティ投資で対策を進めていますが、背後に外国政府の資金や情報機関がいる場合、一企業の自助努力や民事訴訟だけでは抑止力として不十分です。
■ 要するに、倭国には「誰が、どの情報に、どのような条件でアクセスできるのか」を包括的に管理し、外国政府やその関係機関の指揮・支援を受けた悪意ある情報取得・持ち出しを、平時から一貫して抑えるための横断的な法体系が十分に整備されているとは言い難い状況です。
経済安保分野のセキュリティ・クリアランス制度や重要経済安保情報の保護は大きな前進です。
しかし、国が指定しきれていない段階の先端技術や、重要インフラ企業が自ら保有する運用データなど、いわば「指定の手前」で狙われる領域については、なお保護の空白が残っていると議論されています。
■ 重要インフラや防衛産業が高度にデジタル化し、海外との連携も深まる中で、「内部から狙われる」という前提に立った法整備は避けて通れません。
部分的な対策の積み上げだけでは、国家ぐるみの諜報やサイバー攻撃のスピードに制度整備が追いつかないのではないか、という危機感が専門家の間でもたびたび指摘されています。
だからこそ、内部者リスクも含めて「外国政府やその関係機関のための組織的な情報収集・持ち出し」を明確に対象とし、企業努力だけでは対処しきれないレベルの行為について、早い段階から一貫して対処できる枠組みが必要だと考えます。
■ もちろん、その際には、何をもって「外国政府等の指揮・支援」と評価するのか、捜査手続きの適正や乱用防止の仕組みをどう担保するのか、といった点もセットで丁寧に設計しなければなりません。
ここがあいまいなままでは、国民の知る権利や正当な取材、内部告発が萎縮するという懸念が残ります。
■ ここで求められている『スパイ防止法』は、国民の知る権利や正当な取材、内部告発を抑え込むための道具ではありません。
外国政府やその関係組織の主導の下で、倭国の安全保障や経済基盤を損なう目的で行われる悪意ある情報取得・持ち出しを、刑罰と捜査権限の面から明確に位置付け、抑止するための法整備です。
国を守る最低限の備えとして、『スパイ防止法』の制定が不可欠です。 November 11, 2025
4RP
/
Wフォロー&リポスト🔁で
A5ランク【黒】毛和牛🐃
#プレゼントキャンペーン 🎁⚡️
\
📢 応募方法
①クラウドキャッチャー & モコネオ をWフォロー!
@CCatcherApp & @CC_moconeo
② キャンペーン投稿をリポスト🔁
🗓️ 期間:〜11月28日(金)23:59〆
🏆 賞品:A5 黒毛和牛 選べるカタログギフト…抽選1名様
🔽詳細はこちら🌩️
https://t.co/wXPx2dqdwB
#クラウドキャッチャー
#オンラインクレーンゲーム #オンクレ
#ブラックフライデー
#リポストキャンペーン November 11, 2025
4RP
現時点で最高性能を叩き出したコーディングモデル、「Claude Opus 4.5」について知っておくべきことまとめ
Claude Opus 4.5 について重要な情報をまとめました。エンジニア採用試験で人間超えを記録するなど、必見の内容です。
・Anthropic は Claude Opus 4.5 を発表。APIおよび主要3大クラウドで本日より利用可能
・APIモデル名は claude-opus-4-5-20251101。コンテキストウィンドウは200k
・コーディング性能は世界最高。SWE-benchで80.9%を記録し、GPT-5.1やGemini 3 Proを上回る
・必要なツールのみ読み込む「Tool Search」により、オーバーヘッドを約85%削減(コンテキストの95%を実データに活用可能)
・「Programmatic Tool Calling」により、複雑なタスクのトークン数を約37%削減
・デスクトップ版「Claude Code」が登場し、複数セッションの並行実行が可能に
・Chrome拡張機能が全Maxユーザーに拡大、Excel連携もベータ版として提供開始
・価格は/(入力/出力)。前モデルOpus 4の1/3の価格設定 November 11, 2025
2RP
Cloudflare、テクニカルには本当に凄いので、クラウドに携わるエンジニアが一度は触って概要を掴んでおいた方がいいと思う
ただなぁ、大量に著作権侵害ビデオを配信しているサイトはいまだにCloudflareだし、社内も凄まじく、もうちょっと大人にならないと、倭国で売り上げ伸ばせと言われても難しいよなぁ、、、 November 11, 2025
1RP
1. 公文書管理の様々な問題について
公文書の扱いに関し、本年6月及び9月定例会での一般質問に引き続き、以下質問する。
1. 小平市公文書管理規則第10条第1項の「定め」に関する文書の公開請求で、簿冊名と保存年限が記されたファイル情報が公開された。しかしその中には、6月定例会で指摘した、1年未満で廃棄したとする鷹の台駅前広場整備工事に関する協議書・指示書・回答書などについての定めがない。なぜか。規則違反ではないか。
2. 9月定例会で、カメラなど職員の私物への記録は業務上禁止すべきではと質問した。答弁は「業務上、私物の使用を完全に禁止した場合、状況に応じては記録すべきものが記録できないなどの弊害が生じることが予想される」という旨のものだった。「記録すべきものが記録できない」の具体的な想定事例は何か。
3. 公開文書の写しについて、公開漏れの修正分としてCD-R100円分や紙10円分を無償交付した事例を聞いている。いずれも市の損失と考えるが、会計上どう処理しているか。運用の反省や再発防止の取り組みはしたか。
4. 9月定例会で、公開文書の写しをメールやクラウドで交付することについては、現状、紙媒体が多く、一部公開文書の電子化は事務量の増加が課題と答弁した。しかし実務として、黒塗り後にスキャンしてファイル送信するだけではないか。ほかに事務量増加の要因があるのか。3の問題も減り、メリットの方が大きいと思うが見解は。
5. 文書総合管理システムである公開羅針盤V4の説明を見ると、文書作成、メモ作成、掲示板、コメント付与、更新者や更新日時の表示、PDFに手書きできる機能もある。これらの機能によりシステム上に作成・表示される文書も公文書の公開対象になると考えるが、通常そうした情報は公開されていないようだ。なぜ公開されないのか。
6. 9月定例会で、公文書をすべてスキャン・電子化して永遠保存する提案に対し、「公文書の管理は市政が適正かつ効率的に運営されることが目的の一つ。公文書の保存期間はその効力・重要度・利用度・資料価値等を考慮して定める。業務に利用しない、保存が不必要な文書を理由なく保有することは考えていない」旨の答弁だった。しかし、すべての文書を電子化して保有することによる(主に電子化と検索の)コストより、効力・重要度・利用度・資料価値等を一つ一つ検討してさらに期限管理するコストの方が、著しく大きいものと考えるが見解は。
7. 9月定例会で、電子決裁率は現時点で約74%と答弁した。ここ数年、電子決裁率が向上しない主因は何か。
8. 例えば、教育委員会指導課の電子決裁率は市として積極的に公開していないと聞いた。その理由は何か。
9. 公開決定等の期限は原則として公開請求日翌日から14日以内だ。一方、一部公開時の黒塗り作業等に要する時間はその期限に含まれていないということは市の条例や取扱要綱を読んでも分からない。そこで質問する。
① 黒塗りに2週間程かかった事例があると聞く。公開決定の速やかさは求められているのに、その後の黒塗りについての速やかさは求められていないのか。見解は。
② 小平市情報公開事務取扱要綱の第8条(公開請求書を受け付けた場合の説明等)(1)に、黒塗り作業などの実務に別途時間を要する場合がある旨を追加すべきではないか。
10. 小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会の会議録は過去3年分程度を市ホームページで公表する運用としている。しかし同審議会は情報公開の総合的な推進のためにある。期限を設けず掲載してはどうか。
11. 市民が市教育委員会に学校いじめ対策委員会協議録の保存期間に関する公文書を請求したところ、個別に定めていないため作成しておらず存在しないと非公開決定された。しかし小平市立学校公文書管理規則第18条に「校長は、文書保存期間表に従い、公文書の保存期間を定め、その保存期間が満了する日までの間、当該公文書を保存するものとする。」とある。保存期間の定めは意思決定で、公文書に残るはずだ。なぜないのか。
12. 学校いじめ対策委員会で、協議録や会議録などの記録を公文書として残していない事例があると聞く。市教育委員会は記録を残すよう指導していると言うが、実際に記録を残していない事例数と対応策は。
13. 保存年限を過ぎていても文書が残っていれば公開対象になる。しかし周知不足のためか、市教育委員会への公開請求で「保存年限を過ぎたものは公開対象ではない」として別の文書が公開される事例があった(本年1月14日に公開決定通知)。その後、保存年限の超過している残存文書を公開対象に変更し、先の通知を取り消した。これは重要な事案と考えるが、庁内でどう扱ったか。また、取り消し後に改めて公開決定通知が出されたのが本年6月23日だったという。14日や60日のルールは適用されないのか。状況の説明を求める。 November 11, 2025
「Gemini3.0が凄い、生成AIはGoogleの勝利決定( ー`дー´)キリッ」
って話題が多いが、ほんの2ヶ月前、GeminiにGoogle WorkspaceのGmailが英語設定になるのを倭国語設定にする変更方法を聞いたら泥沼化でワケがわからなくなり、MicrosoftCopilotに聞いたらスパッと治った事実があるので、あんましアテにするのはどうかなと。
またGeminiは我田引水で、なるべくGoogleクラウド系のAI(Claude)に誘導しようとするので油断も隙もないw November 11, 2025
――――🖤💜0時投入START💜🖤――――
<11/26㊌>
✅#クロミ 20周年クリアポフィ
――――――――――――――――――
▼ゲームプレイはこちら
https://t.co/vVD81fRwXZ
#クラウドキャッチャー
#オンラインクレーンゲーム
#オンクレ https://t.co/P82jPIcfsf November 11, 2025
ClaudeデスクトップアプリにClaudeCodeが登場!
これはClaudeアプリからコードを見ることなく、自然にクラウド上・ローカル上両方で開発できます
最近話題になった Antigravityのように より自然に開発できるのが最高ですね https://t.co/15GbFyCpuj November 11, 2025
クラウドとオンプレのハイブリッド構成を理解できる人は重宝されます。一方で取っ付き辛さ難しさを感じている人は基本的なネットワークの理解が乏しいからです。自分の実力を試す意味でもこの記事を理解できたら合格です。とても良い内容なので、ぜひ。
https://t.co/hPPsWIXzKj November 11, 2025
9Sはクラウド…と言いたいところだけどウェアがマリタイムと被りそうなので若セフィが良いような クラウドかザックスでニーアとか アダムとイヴもあるけど…ソルジャーたちペア組んでやってみてほしい… デボポポとかカイネとかもほしい あとヨナのあの衣装だれか着て… November 11, 2025
#オンクレ オリジナル #ショートドラマ
第5話「失望 前編」公開中✨
https://t.co/qmqg2IBdna
ぜひご覧ください👀💓
#クラウドキャッチャー #オンラインクレーン November 11, 2025
📊「レジ締めが毎日大変…」
「売上 在庫 スタッフ管理バラバラで非効率…」を解決💡
📌セルフオーダー&キャッシュレス連携で回転率UP
📌多店舗展開でも本部で一元管理OK
📌データ分析で売れる/ムダを減らすが可視化
人手が足りないオーナーの味方クラウド型POSレジ📈
[PR]
https://t.co/0NulaWJPMh November 11, 2025
【チャンピオン -京都本店-】 販売情報🔥
クラウドのフィギュアご購入いただきました!!
お買い上げありがとうございます🙇
チャンピオンでは買取も実施中🔥
https://t.co/rFqd9nzsB5
#フィギュア #ファイナルファンタジー #買取 #無料査定 #河原町 #祇園 #京都 https://t.co/Tbu9sTEUIr November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。