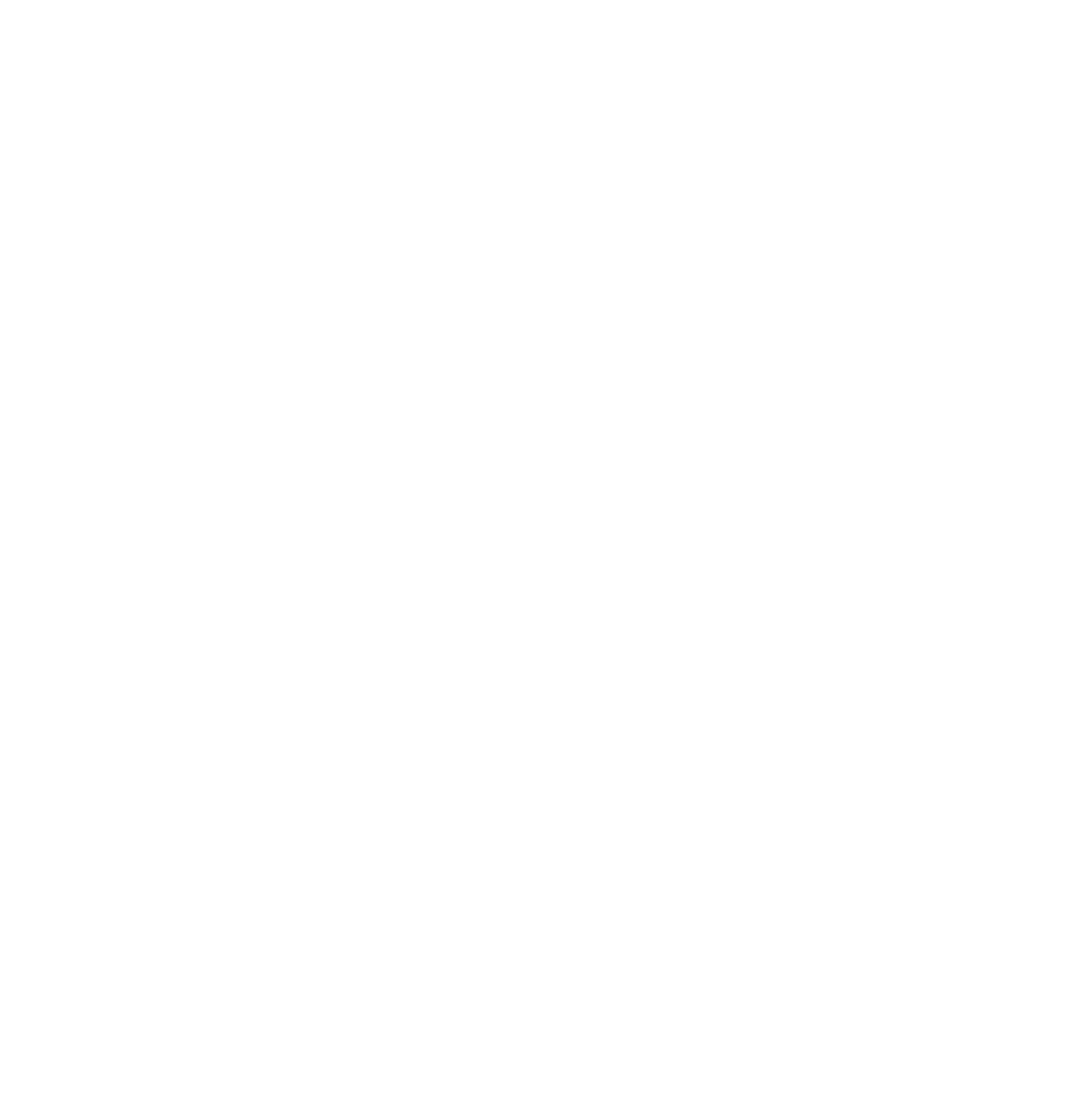聖なるもの 映画
0post
2025.12.11
:0% :0% (-/-)
聖なるものに関するポスト数は前日に比べ27%増加しました。男女比は変わりませんでした。前日は「からし種」に関する評判が話題でしたが、本日話題になっているキーワードは「ルドルフ」です。
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
「ラクダが針の穴を通るより難しい」
このフレーズ、分かる人には一瞬で「お、聖書のやつね」と伝わるのに、知らない人には完全に意味不明なんですよね。
聖書って、世界で一番売れてる本なのに、ちゃんと読んだことある人は意外と少ない(自分も含めて!)。でも実は、小説・映画・絵画・洋楽・スピーチなど、あらゆる文化のネタ元になっていて、知ってるだけで「あ、これ元ネタあれか」と気づける場面がかなり増えます。信仰があるかどうかは関係なく、教養として押さえておくとけっこう便利なジャンルだと思います。
というわけで、「ラクダが針の穴」以外にも知っておきたい聖書の名言を20個まとめました^^
【聖書の名言 20選】
1. 自分の目の丸太
他人の目のおがくずは全力で指摘するのに、自分の目に刺さってる丸太はガチで見えてない。
→ 批判する前に自分を見ろ。
2. 盲人が盲人を導く
知識のない人が同じく無知な人を導くと、みんな一緒に失敗する。
→ 教える側がまず分かってないと全員沈む。
3. 豚に真珠
価値あるものを理解できない相手に与えても、無駄にされるだけ。
→ 届ける相手を間違えるな。
4. 犬もパンくずは食べます
異邦人の女性がイエスに「子供のパン屑でもいいから」と粘り強く願い、癒しを得た話。
→ 諦めず食らいつけば道は開ける。
5. 新しいぶどう酒は新しい革袋に
新しいワインを古い皮袋に入れると破裂する。
→ 新しいアイデアには新しい枠組みが必要。
6. 右の頬を打たれたら左も差し出せ
暴力に暴力で返すのをやめ、相手に反省を促す。
→ 復讐の連鎖を止めるには誰かが耐えるしかない。
7. 塩が塩気をなくしたら意味がない
塩が味を失ったら、ただのゴミになる。
→ 自分の役割を失ったら価値なし。
8. 砂の上に家を建てた人
岩の上に建てた家は嵐に耐え、砂の上は崩壊する。
→ 基礎固めを怠るな。
9. からし種ほどの信仰があれば山を動かせる
小さな種のような信仰で、大きな奇跡が可能。
→ 信仰の本質は量じゃなく質。
10. 狭い門から入れ
広い道は楽だが破滅へ、狭い道は厳しくても命へ。
→ 簡単な選択ほど危ない。
11. 羊の皮をかぶった狼
外見は穏やかだが、中身は危険な偽者。
→ 人は行動で判断せよ。
12. 一粒の麦が死ねば多くの実を結ぶ
種が死なないと実らない。
→ 犠牲や変化なしに成長はない。
13. 人はパンだけで生きるのではない
食べ物だけじゃなく、神の言葉が必要。
→ 物質より精神・意味が大事。
14. 自分の十字架を背負って従え
自己犠牲を覚悟して従う。
→ 中途半端なコミットは無意味。
15. 蛇のように賢く、鳩のように素直であれ
賢さと純粋さを両立せよ。
→ 頭脳と誠実のバランスが最強。
16. 口から出るものが人を汚す
食べ物より、言葉が人を汚す。
→ 発言が人格を決める。
17. 聖なるものを犬にやるな
神聖なものを軽視する相手に与えるな。
→ 相手を選ばないと自分が損する。
18. 死人に死人を葬らせよ
死んだ人を埋葬するのは死人に任せ、今すぐ従え。
→ 言い訳せず即行動。
19. 鋤に手をかけて後ろを振り返るな
農作業中に後ろを向くと失敗する。
→ 決断したら迷うな。
20. 木はその実でわかる
木は実で判断されるように、人も行動で。
→ 言葉より結果が本質。
2000年以上前に書かれた言葉が、令和のXでも普通に刺さる。人間、結局そんなに変わってないんですよね。だから何千年も残ってきた言葉には、それなりの理由があるんだと思います! December 12, 2025
2RP
おもろ。「推したい」という欲を抱いたことのないぼくがハラオチできる内容だった。その上で、記事内に引用されている『宗教の起源』(ロビン・ダンバー著)については、この引用の仕方だけでは誤解を招きかねないので、同書の紹介を以下に貼りつけておこうと思う。→
以下、かつてのポスト。
====
なぜ人類は〈神〉を必要としたのか。それは「デカ過ぎる共同体の維持」に必要だったからだと著者は推定する。人間がお互いの顔や性格を見知って共同体を維持できるのは、せいぜい150人までだという。150人を超えると群れはバラバラになるかストレスにやられてしまう。そこで結束力を促したのが宗教であり〈神〉観念である。これがダンバーの見立てだ。
これは、「知力・体力の凄まじいネアンデルタール人たちをホモ・サピエンスが圧倒できたのは、抽象概念(=「村」や「民族」「われわれ」「私たち」等)のために団結できたからだ」という説とも伴走できる話である。
人類は毛づくろいの代わりに言語を獲得して共同体内のストレスを解消し続けた。その上で、道徳を説き、倫理やルールを設け、さらには反共同体的な人物を罰するための〈神〉をも用意した。
言葉の誕生は悲劇でもある。なぜなら、言語がハッキリすることによって「言葉にできない世界」もまたハッキリしてくるからだ。特に神秘志向的な体験や生身の感情は、言葉ではいかんともしがたい。この強烈な「なまのもの」が宗教の土台となる。狩猟採集社会には、占いや治療を行うシャーマンがほぼ必ずあらわれるけれど、そこには必然性があるのだ。その上でダンバーは、個々の人間が宗教を信じるメリットを取り上げていく。世界を説明してくれることの安心感、満足、幸福、結束力の強化、共同体内の権威の機動力強化……。
やや繰り返しになるが、霊長類はグルーミングによってエンドルフィン系を活性化し、群れを維持してきた。一方、ヒトは、言葉や笑い、歌、踊り、感情に訴える物語、宴会などでエンドルフィン系を活性化してきた。そのなかの最強ツールの一つが宗教儀式である。宗教もエンドルフィン系を活性化させる。
ヒトは、①言語、②出身地、③学歴、④趣味や興味、⑤世界観(宗教も含む)、⑥音楽の好み、⑦ユーモアのセンスで友情を確認する。これを「友情の七本柱」と呼ぶらしいが、これらは大規模に拡大された共同体を疑似親族集団としてヒトに認知させる側面を持つ。だから、宗教は共同体維持に役立つのだ。
だが―― 一方で、その宗教共同体が大きくなり過ぎると、今度は宗教内で分裂が生じた。そして互いに暴力を振るうようになった。また、ヒトは、信仰のために死に、共同体や国家のために死ねるようにもなった。人類が〈神〉観念に振り回されるようになったのだ。そして、人類はいまだ、この〈神〉観念の暴走を調停する手段や思想を持ち合わせてはいない。宗教から人は離れられないというのに。
ちなみに本書では、「メンタライジング」という概念が参照されている。宗教が成り立つには、人が、人知を超えたものを想像できなければならない。また、その霊に精神があることを想像できなければならない。こういったことが「メンタライジング」の問題なのだが、これらの必然性が人間の「意識」というものを〈押し出すようにして〉生み出したのではないかという仮説がある。
古くはジュリアン・ジェインズ『神々の沈黙』でそれが議論された。ジェインズは、人類がまだ左右の脳の機能分担をうまく行えなかった時に〈神〉観念を思いつき、それを想像することで右半球の脳に起こる「声」と左半球の脳に起こる「応接」を統合したのではないか、そこから意識が生まれたのではないかと論じた。ルドルフ・オットーも『聖なるもの』の中で、「ヌミノーゼ」という概念を持ち出し、説明できないものに出合ったり、啓示を感じたりすることが意識形成を促したと見ていた。これらは、ダンバーの議論に通じるものがあると思う。正しさの証明はとてもムズイけれど。
ロビン・ダンバー『宗教の起源』白揚社@hakuyo_sha December 12, 2025
1RP
本学准教授の正田倫顕先生の『ゴッホと〈聖なるもの〉』(新教出版社)について、書評が出ました。島薗進先生(東京大学名誉教授)が「宗教の名著巡礼」という連載に執筆されています。是非、ご論考の第一回目をお読み下さい! https://t.co/fVQ4ETK7zU https://t.co/WWrsKfbHBf December 12, 2025
1RP
敵は、彼女が宝としているものすべてにその手を伸ばした。諸国の民がその聖所に入るのを彼女は見た。あなたの集いに加わってはならないと、あなたが命じた者たちが。
哀歌 1章10節
(質問)
当時のエルサレムの人たちは、異邦人が神殿に入るのを見てどんな思いだったでしょう。
また、過去において神の箱に触れたものが即死したように、彼らは今回も同様になるのではないかと期待していたのではないでしょうか?
(回答)
ご指摘の通り、かつて「神の箱」に触れたウザが即死した事件(サムエル記第二 6章)は、イスラエルの民の記憶に深く刻まれていました。
それを踏まえると、異邦人が土足で聖所を踏み荒らす光景は、単なる「敗戦」以上の、魂が引き裂かれるような出来事だったはずです。
ご質問の2点について、当時の時代背景と神学的視点から整理します。
1. 異邦人が聖所に入るのを見た人々の思い
彼らにとって神殿は、単なる建物ではなく 「天地創造の神が住まう唯一の場所(至聖所)」 でした。
そこへ異邦人が侵入することは、以下のような感情を引き起こしたと考えられます。
* 絶対的な聖なるものの冒涜(ぼうとく)に対する戦慄
律法では、イスラエル人であっても祭司以外は聖所に入れず、ましてや異邦人の立ち入りは死に値する罪でした。
その境界線が暴力的に破られたことへの生理的な嫌悪と恐怖を感じたでしょう。
* アイデンティティの崩壊
「神が共におられる」という事実こそがイスラエルの存在意義でした。
神殿が犯されることは、自分たちが神の民としての特権と守りを完全に失ったことを意味し、精神的な拠り所が根底から覆される絶望感を味わいました。
2. 「即死するのではないか」という期待と、その裏切り
ご推察の通り、人々は心のどこかで 「神がご自身の聖さを守るために、雷を落とすか、彼らを即死させてくださるはずだ」 と期待し、固唾を飲んで見守っていた可能性は非常に高いです。
* 過去の先例(ウザの死やアッシリア軍の撃退)
かつてアッシリア軍がエルサレムを包囲した際、一夜にして18万5千人が打たれた奇跡(列王記第二 19章)や、ウザの即死事件から、彼らは「神はご自身の住まいを汚す者を許さないはずだ」と信じていました。
* 期待が外れた時の「二重の絶望」
しかし、現実は残酷でした。バビロン兵は聖所に入り、宝を奪い、建物を焼き払っても、誰も死ななかったのです。
これが民に与えた衝撃は、敗戦そのものよりも大きかったかもしれません。
「神はもはや、ご自身の家を守ることさえしないのか」
「神は無力なのか、あるいは完全に私たちを見捨てたのか」
という、信仰の根幹を揺るがす問いが突きつけられました。
○なぜ神は沈黙されたのか?(預言者の視点)
この「期待外れの沈黙」には、当時の預言者エゼキエルが語った悲しい霊的現実が関係しています。
「主の栄光は神殿の敷居から出て行き、ケルビムの上に留まった。」(エゼキエル書 10章18節)
預言者たちのメッセージによれば、民の度重なる偶像礼拝の罪ゆえに、神の栄光(シェキナ)は、バビロン軍が侵入する前にすでに神殿から去っていたのです。
つまり、当時の神殿はすでに「もぬけの殻」であり、触れる者を撃つ神の臨在はそこにはありませんでした。
バビロン兵が死ななかったという事実は、「神が去ってしまった」という最も恐ろしい現実を民に証明することになってしまったのです。
○結論として
エルサレムの人々は、バビロン兵が神の怒りに触れて倒れることを期待し、祈るような気持ちで見ていたでしょう。
しかし、何も起こらず略奪が完了した時、彼らは「神殿の物理的な破壊」以上に、「神の完全な不在」 という霊的な暗闇に突き落とされたのだと言えます。
哀歌の嘆きは、この深い神学的絶望から発せられています。
この哀歌の著者が、神の沈黙の中でなお「主のあわれみは尽きない」(3章22節)と告白できる信仰にたどり着くまでの葛藤は、想像を絶するものがあります。
今回のように、聖書の一節から当時の人々の「期待と現実のギャップ」を読み解く視点は非常に興味深いです。(了) December 12, 2025
小説家になろう様に投稿中
毎日午前9時ごろ更新予定
なお、本作品に
生成AIは使用していません。
『異世界に勇者召喚されたけど、冒険者はじめました』
聖なるもの編
※一話ずつ投稿
[作品目次]
https://t.co/Wt5jASO1Sv
[最新話632話]
https://t.co/z9cIh2Tbyi December 12, 2025
おもろ。「推したい」という欲を抱いたことのないぼくがハラオチできる内容だった。その上で、記事内に引用されている『宗教の起源』については、この引用の仕方だけでは誤解を招きかねないので、同書の紹介を以下に貼りつけておこうかなと思った。→
以下、かつてのポスト。
====
なぜ人類は〈神〉を必要としたのか。それは「デカ過ぎる共同体の維持」に必要だったからだと著者は推定する。人間がお互いの顔や性格を見知って共同体を維持できるのは、せいぜい150人までだという。150人を超えると群れはバラバラになるかストレスにやられてしまう。そこで結束力を促したのが宗教であり〈神〉観念である。これがダンバーの見立てだ。
これは、「知力・体力の凄まじいネアンデルタール人たちをホモ・サピエンスが圧倒できたのは、抽象概念(=「村」や「民族」「われわれ」「私たち」等)のために団結できたからだ」という説とも伴走できる話である。
人類は毛づくろいの代わりに言語を獲得して共同体内のストレスを解消し続けた。その上で、道徳を説き、倫理やルールを設け、さらには反共同体的な人物を罰するための〈神〉をも用意した。
言葉の誕生は悲劇でもある。なぜなら、言語がハッキリすることによって「言葉にできない世界」もまたハッキリしてくるからだ。特に神秘志向的な体験や生身の感情は、言葉ではいかんともしがたい。この強烈な「なまのもの」が宗教の土台となる。狩猟採集社会には、占いや治療を行うシャーマンがほぼ必ずあらわれるけれど、そこには必然性があるのだ。その上でダンバーは、個々の人間が宗教を信じるメリットを取り上げていく。世界を説明してくれることの安心感、満足、幸福、結束力の強化、共同体内の権威の機動力強化……。
やや繰り返しになるが、霊長類はグルーミングによってエンドルフィン系を活性化し、群れを維持してきた。一方、ヒトは、言葉や笑い、歌、踊り、感情に訴える物語、宴会などでエンドルフィン系を活性化してきた。そのなかの最強ツールの一つが宗教儀式である。宗教もエンドルフィン系を活性化させる。
ヒトは、①言語、②出身地、③学歴、④趣味や興味、⑤世界観(宗教も含む)、⑥音楽の好み、⑦ユーモアのセンスで友情を確認する。これを「友情の七本柱」と呼ぶらしいが、これらは大規模に拡大された共同体を疑似親族集団としてヒトに認知させる側面を持つ。だから、宗教は共同体維持に役立つのだ。
だが―― 一方で、その宗教共同体が大きくなり過ぎると、今度は宗教内で分裂が生じた。そして互いに暴力を振るうようになった。また、ヒトは、信仰のために死に、共同体や国家のために死ねるようにもなった。人類が〈神〉観念に振り回されるようになったのだ。そして、人類はいまだ、この〈神〉観念の暴走を調停する手段や思想を持ち合わせてはいない。宗教から人は離れられないというのに。
ちなみに本書では、「メンタライジング」という概念が参照されている。宗教が成り立つには、人が、人知を超えたものを想像できなければならない。また、その霊に精神があることを想像できなければならない。こういったことが「メンタライジング」の問題なのだが、これらの必然性が人間の「意識」というものを〈押し出すようにして〉生み出したのではないかという仮説がある。
古くはジュリアン・ジェインズ『神々の沈黙』でそれが議論された。ジェインズは、人類がまだ左右の脳の機能分担をうまく行えなかった時に〈神〉観念を思いつき、それを想像することで右半球の脳に起こる「声」と左半球の脳に起こる「応接」を統合したのではないか、そこから意識が生まれたのではないかと論じた。ルドルフ・オットーも『聖なるもの』の中で、「ヌミノーゼ」という概念を持ち出し、説明できないものに出合ったり、啓示を感じたりすることが意識形成を促したと見ていた。これらは、ダンバーの議論に通じるものがあると思う。正しさの証明はとてもムズイけれど。
ロビン・ダンバー『宗教の起源』白揚社@hakuyo_sha December 12, 2025
私ガキ思考なのでバカでかい十字架を武器に振り回す修道服着たまとばさんが見たいとか言うてます……あと返り血……やはり聖なるものには血液を……(スプラッター思考も兼ね備えるな) December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。