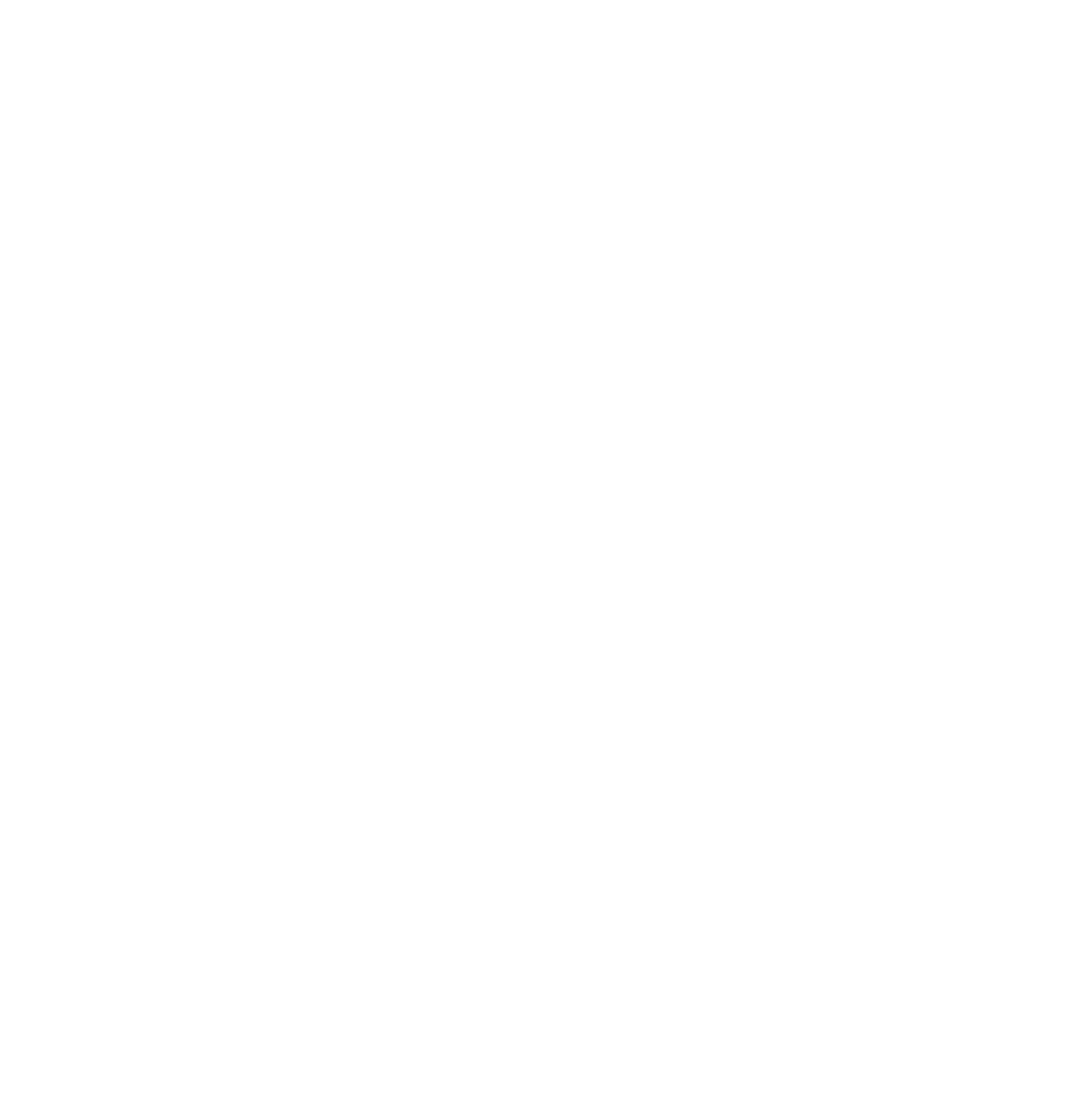カトラリー トレンド
0post
2025.11.29 06:00
:0% :0% (-/-)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
ハルピンはロシア料理が有名だそうで、老舗の波特曼西餐庁へ。建物こそ立派だが、お味は正直言って学校給食の延長線みたいな感じ。何よりカトラリーは洋式なのに、サーブの仕方がそこらの食堂と同じで適当なところに料理をボンと置くから、いちいち自分で皿を動かさないといけないのが謎。それでいて安くない。このアカウントで言った記憶がないのですが、再訪はナシです。 November 11, 2025
1RP
カトラリーを持った手の素材を作ってみました!
いい肉の日も近いので…!
おまけで舌を出した口をつけました!
◯トリミング、カラー変更など
❌️自作発言
商用利用も大丈夫です!
モデル:おりりん様(#olilinusa)
#Vtuberフリー素材 #Vtuber素材 https://t.co/JeZi4IDtVk November 11, 2025
カトラリー「ねえファル、しりとりしようよ。しりとりのり!」
ファル「なんですかいきなり。リール」
カ「ルビー」
フ「イスタンブール」
カ「ルーレット」
フ「トリコロール」
カ「ルービックキューブ」
フ「ブラックホール」
カ「る…る…あ、ルール!」
フ「ルノワール」
カ「もうやだ」 November 11, 2025
すぎらいと夢載せられるから編集版載せる❣らいとくん苗字頂戴❣
.
「ピノコニーに行きたい、だと?」
なんでもない食事の時間のはずだった。いつも通りディナーを食べ、デザートを楽しみ、シャワーを浴びて彼女を抱いて眠って終わる。なんてことのない一日を終えるはずだった。
「さっき、バーでアベンチュリンさんがピノコニーの話をしてくれて……、とても有名なアニメだとかフィルムがあるんですって。スギライト様も最近働きづめで息抜きできていないみたいですし、折角だから、と」
楽しそうに話す彼女をじっと見つめる。その顔の綻び方から、大方奴の話術に乗せられたのだろう。
彼女のためなら何でもすると誓ったスギライトでも、アベンチュリンという男がきっかけなのはどうにも気に食わなかった。『それならアベンチュリンといけばいい』と言えれば良かったものを、そうすることもプライドが許さない。そもそも、自分以外の異性と彼女がどこか知らない場所で笑っていることなど考えたくもなかった。想像するだけで、先ほどまで食べていたものを吐き出しそうになる。
「……だめ、ですか?」
黙ったままのスギライトを気に掛ける。その声で静かに我に返ると、止まったままだった食事の手を再開した。
「……、そう急いで決めることじゃないだろう。その話はまた明日だ」
それを肯定と取った彼女はどこか浮足立った様子ではい、と返事した。スギライトは作業のようになった食事を進める。もう目の前のステーキは何の味もしないゴムのようだった。
「今日のスープは美味しいですね!」
明るく笑う彼女をじっと見る。その笑顔は俺だけのものになったはずだ。どうして他人に見せる。しかもよりにもよって、あんな男を。
「……そうだな。俺が直々に作らせたんだから、当然だ」
「そうだったんですね!流石です」
彼女が褒めるので、スギライトもスープを口に含んだ。あんなにもこだわったはずのコンソメスープはこれっぽっちも味がしなかった。
***
彼女と出会ったときから、この女は自分のものにしてやる、と決めていた。それはアベンチュリンも一緒だったようで、スギライトが見ていない隙に彼はよく彼女をデートに誘っていた。二人の男の醜い欲望に絡まっているとは知らない彼女はただ二人の誘いを受けていた。そんな純粋さも、自分の薄汚い欲に気付かない様子も全部愚かに見えた。スギライトの好意など気付いていないというフリをするアベンチュリンのことも。
そんなときに転機が訪れた。アベンチュリンが仕事で、ピノコニーに長期出張をするという話が耳に入った。スギライトはアベンチュリンを見送りに行く。
「君が見送りだなんて。明日は君の愛用しているカトラリーが降ってきそうだ」
「……冗談はよせ。まさかお前がピノコニーに行くとはな」
「〝まさか〟?それはこっちのセリフさ。願ってもないチャンスだ。そうだろう?」
かけていたサングラスをとりながらスギライトに一歩近づいた。背丈はスギライトのほうが高く、自然とスギライトはアベンチュリンを見下ろす形になる。近くで見れば、その自信たっぷりな表情がひどく憎く見えた。
「彼女をモノにするチャンス。何せ僕がいなくなるんだ、はは、君も幸運だね」
「随分余裕があるな。ああ、余裕しかないんだったか」
「僕がピノコニーに行って帰ってきたら、君たちの仲がどうなっているか楽しみだよ」
『君が彼女をモノにしたとしても、僕は奪い返せる』とでも言いたげな表情をした彼はサングラスをかけなおし、スギライトに挨拶もなしにとっととその長い旅路に足を踏み入れていった。
「……楽しみ、楽しみだと?生意気なことばかり」
苛立っていた。何より呪いをかけられた気分だった。奴がいない間、ゆっくり彼女を知ることが出来ると思ったのに、そんなスギライトのアプローチも無駄に終わるのではないかと。
「そんなこと、あってたまるか」
彼女は俺のものだ。呪いだというなら受けて立ってやろうではないか。スギライトは荒々しく手袋を外すと付き添っていた従者に押し付け、食事の時間まで部屋に入るなと言いつけた。
部屋に戻ると、いつもは料理が整列している大きなテーブルはただ真っ白なテーブルクロスが広がっているのみで、普段に比べると随分殺風景だった。そこの席に座っている彼女のもとへ行くと、先ほどまでの苛立ちをどうにか抑え、冷静を装ってスギライトは声をかけた。
「この時間はなにもないのに。珍しいな」
「スギライト様が、アベンチュリンさんをお見送りしたと伺ったもので。戻ってくるならこの部屋を通るかと思ったんです」
そう言って微笑む彼女を見ていると、彼女はスギライトを心から好いているのではないか、という錯覚を覚える。
「……お前は、アベンチュリンをどう思っている」
「え……っと、それはどういう意味ですか?」
「なんでもいい。お前の奴への感情を教えろと言ってるんだ」
「優しい方だな、と」
どうしてそんなことを聞くのだろう、と不思議そうな顔で聞く彼女に、静めていた怒りがふつふつと湧きあがる。
「俺の事はどう思っている」
「スギライト様は命の恩人です。それに私を大切にしてくださっているし……」
違う。そんなありきたりな言葉が聞きたいわけじゃない。その先の言葉を知りたいのだ。
彼女の髪を撫でてすくう。艶のある髪は上質なシルクよりもずっと価値があるだろうと思わせる美しさで、そのほんのり桃色に染まった頬はどんな化粧品でも再現できない。宝石のような瞳も、果実のような潤んだ唇もなにもかも、値がついていたらどんなに良かったか。お前を買えればどんなに気が楽だったか。
「……スギライト様」
珍しく手袋をしていない彼の手にそっと重ね、体温を感じた。彼女の白い肌とは対照的な褐色の肌。よく触れると分かる男性特有の骨ばった指先が、彼女の頬に触れた。確かに熱があった。
「……俺はお前を愛している。誰よりも」
そう呟いたあとに、唇を奪われる。スギライトは確かに自分のものにできるという確信があった。何故なら彼女を心から愛していたから。
***
翌朝、身支度をしていると昨晩の会話を思い出した。――ピノコニー。どんな場所かは知っている。事件があってから現在は順調に復興していると聞いた。
―――やはり気に食わない。こんなことなら、自分から誘っておけばよかった。乱れる心情が手元に反映され上手くネクタイが結べない。そんなときにノックが部屋に響く。
「入れ」
「あ、おはようございますスギライト様、よく眠れましたか」
「ああ……まあな」
「ネクタイが。私が結びましょうか」
「……頼む」
ネクタイから手を離すと、彼女が丁寧に結びなおしはじめる。するすると慣れた手つきで進めていく彼女をじっと見つめているとどこか気まずそうな顔をする。
「そんなに見られると、なんだか恥ずかしいです」
「お前を見ずに何を見るんだ」
スギライトがそういうのと同時に結び終わったようでそそくさと手を離す彼女。もう少し触れてくれてもいいではないか、とその離れた手を掴んで一緒に腰も引き寄せてやる。ヘアオイルをつけたばかりなのか、それとも香水をつけたのかいい香りがする。
「スギライト様……」
「……昨晩の話だが、条件つきなら行っても構わない」
「条件、ですか?」
「ふふ、なんだと思う?」
「う~ん……、ずっと一緒にいる、とか?」
「お前がそういうならそうしよう」
髪越しの額にキスを落とす。
「あ!引っかけたんですか!?」
「人聞きが悪いな」
もう、と頬を膨らます彼女は小動物のようで愛らしかった。実際他に条件はあった。だがそれを彼女に打ち明けたところで、ただ大人げない、器の狭い男だと思われるだけだとスギライトは思った。確かに出先でアベンチュリンという男の名前を出されるのは不満が残る。彼女と二人きりの旅行なのだ。なんの不満も蟠りもなく円満に終わらせたい。
「スギライト様ってば、たまに意地悪するんですから」
「意地悪をする俺は嫌か?」
陶器のような彼女の肌をなぞり、顎を持ち上げる。指が少し食い込んで、彼女の柔らかい頬がふに、と押されている。
「……いやじゃないです」
「フッ、良い子だ」
拗ねたように口をとがらせる彼女の唇にキスをひとつ落とす。恥ずかしさか何かで目に涙を蓄えている彼女は偽物のようだった。あまりに完璧すぎる。全てが。
名残惜しく手を離すといつも通りに今日の予定を伝える。今日戻ったらピノコニーについて話そうというと子犬のように喜んだ。
*
一日を終える。今日は随分長く感じた。ジェイドと仕事していると何かと面倒ごとに巻き込まれる。自分に与えられた仕事だけをこなし終わりたいスギライトはいつも以上の疲労を抱え邸宅に戻る。
乱れたスーツを整え、広間を訪れる。ただいまというはずだった。
「やあスギライト。おかえり」
「おかえりなさい、スギライト様」
どうしてここにいる。その言葉を飲み込んで、スギライトはただただ平常心を保ちいつもの席に座った。
「ピノコニーに行くことになったなら、と色々教えていただいてたんです」
「……そうか。それは良かったな」
「おや?君らしくないね。今日の仕事は随分、ハードだったみたいだ」
「そうでもない。俺にとってはな」
「ああそうだ、スギライトもどうかな?ピノコニーに行くんだろう?僕の案内が、」
アベンチュリンの話の途中で卓上ベルが鳴らされる。
「……これから食事だ。お前の分は用意していない。突然の訪問だったからな」
「……そうみたいだね」
「彼女に用があるなら今度は是非、俺のいる間に来てもらえるか?お前のピノコニーの話は、俺も気になるからな」
「……今度はそうするよ」
テーブルに置いてあったハットをつかみ被ると、スギライトの目を見つめながらアベンチュリンは邸宅を後にした。彼のつけている香水が漂っている。これからディナーだというのに、マナーのない男だ。
卓上ベルを聞いた召使が続々と料理を運んでくる。トマトをメインに使用したオードブルがスギライトと彼女の前に置かれた。
「さて」
彼女には、スギライトのそのセリフがどういう意味だったのかわからなかった。食事をはじめようとしているのか、勝手にアベンチュリンをあげたことについて言っているのか。
上品な動作でカトラリーを持ち上げ、ゆっくりとオードブルに手をつける。
「……食べないのか」
「ああ……ごめんなさい、いただきますね」
スギライトが怒っている。彼はいつも怒っているときほど本題を後回しにする。ふたりの静かな咀嚼音が響く。
「……あ、あの、スギライト様」
「今日のデザートはタルト・オ・フランボワーズだそうだ。好きだっただろう?」
にこりと笑う。
「そ、そうです、でも、あの、」
「スープは以前お前が美味しいと褒めたものと同じものを作らせた」
「うれ、しいです、だけどスギライト様、」
途端がしゃん、とスギライトがカトラリーをテーブルに叩きつけた。
「言い訳があるなら言ってみろ」
ポワソンや、アントレで使うはずのナイフをそっと取り上げる様子から目が離せないまま、これ以上神経を逆撫でしないよう話を紡ぐ。
「勝手に家にあげてごめんなさい、でも断れなくて、それにピノコニーのことは私、わからなかったから、……スギライト様がいるときにすれば良かった。本当にごめんなさい」
「……それで?他には何を話した」
「何も話していません、本当に……だからお願いです、ナイフを置いてください」
革手袋がぎりぎりと音を立て恐怖を煽る。
「スギライト様……」
「……」
大きなため息をついて、ナイフを元あった場所に戻すとスギライトは立ち上がって彼女のもとに跪いた。
「すまなかった」
手を握りその目を見つめた。彼女を怖がらせてしまった。例え原因がアベンチュリンのせいだったとしてもこれは乱れ過ぎたと、スギライトは思った。
元来スギライトは気が長いほうではなかった。好きな女のことになれば尚更である。彼女のその愛おしい声で自分以外の名前を呼ばれればそれだけで気が触れそうだった。だがそれは彼女を傷つけていい理由にはならない。
「……スギライト様、私は、」
「何も言わなくていい。俺が悪かった」
細く美しい指先に口づけを落とす。そこから手首へ移動し、顔をあげて彼女の頬や首にも。
「どうか許してくれ」
耳に響くような低く甘い声で囁き、その赤く染まった耳もまるで料理の味見をするように優しく触れた。
「……ずるいです、そうすれば私が許すと思って」
「許してくれないのか?」
彼女の唇は、ナパージュでコーティングされたフルーツのようだ。潤いがあって、味わえばほんのり甘味を感じる。ショートケーキにひとつだけ乗せられた特別感のある苺のように、何度も何度も欲しくなる。独占したくなるのもきっと一緒だ。
キスというのは、愛を食べる行為なのではないか。スギライトは唇を重ねながらそんな風に思った。
舌の上で肉や野菜、フルーツを転がし味わうように、彼女の柔い肉ともフルーツとも言えないなにかを味わう。同時に彼女もスギライトの舌を拙く転がした。彼の白くふわりとした、柔らかい髪に触れればますます愛おしくなる。
ふと口を離せば互いの間に銀の糸が薄く引かれた。彼女は顔を赤くし少しばかり息を荒くしている。
「……愛しています、スギライト様」
「それは俺を許すという意図の言葉ととっていいのか?」
「……もう、意地悪」
「好きな相手にほど意地悪をしたくなるものだろう?」
その場を立ち上がり、自席に座り直すと途中まで口をつけていたオードブルを下げさせる。
「それで……、ピノコニーの件だが。どこに行きたい?」
***
騒がしい街だ。そう思った。夢の中とはここまで派手なものだったかと。
ドリームプールを使用し黄金に煌めく世界のなかに入った二人は適当に街を散策した。どこもかしこも賑やかであちこちに風船や自我を持ち歩くパネルなんかもある。非現実的な世界に少し気分が悪くなりそうだった。
「本当に色々ある!」
彼女は随分楽しそうだった。最中、「これずっと気になっていたんです」と言った。明らかにあの男の名前を出さないようしているとすぐに分かった。楽しそうにクラシックスラーダを飲んでいる彼女の髪に触れる。夢の中でもその感触は何一つとして変わらない。
「スギライト様も飲みますか?」
「今だけは、様も敬語もいらない」
「えっ」
彼女にとって、その告白をされた瞬間時が止まったように思えた。あんなに輝いている景色のすべてが霞んで見えた。彼の美しい瞳にはどんな装飾も勝てはしないのだと直感する。かつてスギライトは彼女の髪は絹よりも勝るといったが、そういう彼の髪こそシルクやカシミヤなどよりもずっと美しく価値のあるものに思えた。まるでドールのようだ。白いまつ毛が煌めいてひどく綺麗だ。彼の目に雪が降っているようだと思った。
「……スギライト、……なんだか慣れない」
「これから慣れればいい」
華奢な肩を抱いて彼女を見下ろせばちまちまとスラーダを飲んでいる。久々の休暇。スギライトは空を見上げる。この世界は夜が明けないと聞いた。街の照明にかき消されそうになっている星が見える。
「……お前はきっと、どんな世界でも輝いたままなのだろう」
不意に呟いた独り言は空に溶ける。喧噪に飲まれてしまった言葉を彼女が聞き取ることはなかった。
「レストランとホテルを予約してある。それを飲み終わったら行こう」
そういうと彼女は慌てたように瓶を傾けた。おかしくて、そんなに急がなくていいと笑った。
*
レストランは普段スギライトが食しているようなものを提供している店だった。オードブルからはじまり、スープ、アペタイザー、サラダ……。順番に提供されていく食事を淡々と口に運ぶ。スギライトとしては『悪くない』といったところで、しかし気に入ったかと言われればそうではなかった。ピノコニーのなかでも1,2を争うレストランであったがそんなこと彼には関係なかった。
しかし彼女はどれも美味しい!と頬を綻ばせて喜んでいる。
メインディッシュは牛肉を赤ワインで煮込んだもの。ナイフを少しいれるだけでほろりと崩れる柔らかさを舌の上で堪能する。どこか酸味を感じるソースも悪くない。
「美味しいね」
「そうだな」
「……でもきっと、スギライト、と一緒だから」
肉を切り崩す手が、一瞬だけ止まる。
「それは同感だな」
「……本当?」
顔をあげる。スギライトをそのガラスのような瞳にとらえたまま動かない。二人とも食事の手は止まったまま。この静かに過ぎていく瞬間は何物にも代えがたいものだと思った。
「嘘だと思うか?」
「……ううん。うれしいの」
気持ちを交わす時間というのは心地がいい。心までも自分のものになっていく様を見ているようで。
スギライトはゆっくりと再び食事の手を進めるが、とっくに料理などどうでもよくなっていた。彼女がほしい。全部。
「……スギライト、」
ゆっくりと立ち上がった彼女がスギライトの傍に近寄る。その柔らかい髪をそっと耳にかけてやって、そのこめかみから頬にかけてひとつ、ふたつとキスを落とした。
「まさかお前から口づけをしてくれるとはな」
「……だめ……、です、か?」
「だめじゃない」
唇を食み、そのほんの少しだけ開いた隙間を埋めるように舌を伸ばした。期待に応えるように彼女もまた舌を伸ばし、互いに唾液を送りあった。丁度予約した席は個室だったため、スギライトが呼ばない限り人が来ることはない
***
乱れた服を整え、彼女にもドレスを着せてやる。ほんのりと染まったままの頬と乱れた髪が情事を物語っている。
「ごめんなさい、私、食事中に……」
「構わない。俺も……、はあ、普段はこんなことないんだが」
そう言って席につくと二人の間にしばしの静寂が訪れる。勢いに任せ彼女を抱いてしまった、抱かれてしまった。スギライトは食事に手をつけようとカトラリーを持ち上げるが、どうにも手が進まない。彼女を一瞥すると彼女もまた、カトラリーを持ったまま固まっているようだった。
「……あの、スギライト、さ、……」
「……なんだ」
「……さっき、普段はって……、わ、私だけ、ってこと……?」
恥じらいながら、上目遣いでスギライトにそう問いかける。
「……、俺が、他の女と勢いに任せて関係を持つと思うか」
「だ、だって、慣れてるように見えて、」
「なッ、そんなわけないだろう!」
「じゃっじゃあ、はじめてだったんですか⁉」
「そういうお前はどうなんだ、随分感じて、強請っていたじゃない」
「それはスギライトだからッ……、あ、」
口走ったと顔を覆っている彼女は、耳まで赤くしている。スギライトはたった今言われたことを上手く飲み込めず、一度気分を落ち着かせようとワインを口に含んだ。とりあえず、次の食事を持ってこさせようとベルに触れた。
「あ、あのっ、……、私は、後悔、してません」
「……」
「だから、……これからも傍にいてくれませんか」
「……この程度で俺がお前を、」
そう言いかけ彼女を見ると、体を震わせながらただまっすぐ、スギライトを見つめている。
「……スギライト、は」
「俺もだ。……、最初から、手放すつもりもないが」
柔らかいようで、不敵な笑みを浮かべながら言い放って、彼はベルを鳴らした。次の〝食事〟を楽しむために。
. November 11, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。